【 日光 】<あらたうと青葉若葉の日の光> 聖地...ただ感じるままに
松尾芭蕉の「おくのほそ道」(以下「ほそ道」)の旅は5日目、平野の果てに至った。関東平野の北縁の山々は東北、北陸へ続く。その山地の入り口の一つが「日光」(栃木県日光市)だ。芭蕉の筆にも力が入る。
旅程を「曽良日記」で見ると旅4日目の3月29日、歌枕「室の八島」の参詣を終えた芭蕉と曽良は壬生(みぶ)を経て、楡木(にれぎ)で日光例幣使街道に入り鹿沼で1泊。
翌4月1日(陽暦5月19日。1689=元禄2=年3月は29日までしかなかった)は小雨の中昼ごろ日光に着くと午後、東照宮を参詣。同夜は門前町上鉢石の五左衛門方に泊まった。翌2日は快晴の下、昼まで裏見(うらみ)の滝と含満(がんまん)ケ淵(ふち)を訪れ、そのまま那須方面へ向かっている。
新しい季節祝う
だが「ほそ道」の記述は少し違う。「日光山の麓」到着が「三十日(みそか)」。同夜は五左衛門方に宿泊し、彼の「無智無分別」「正直偏固」な人となりを記す。翌日の「卯月朔日(うづきついたち)」は東照宮を参詣し、裏見の滝を訪れたと書いた。つまり現実にはなかった3月30日があり、参詣と滝見物が4月1日の出来事としてまとめられている。
この違いは芭蕉の演出といわれる。潁原(えばら)退蔵・尾形仂(つとむ)編「おくのほそ道」の註釈では、日光参詣と山巡りの記述をすべて4月1日としたのは「新しい月、新しい季節の始まりを祝うべき日だったから」。宿の主人の俗っぽい記述を参詣の前日とし、霊域・日光の神聖さを強調した構成ということだろう。
東照宮参詣の場面も筆がさえる。今やこの日光東照宮の御威光は一天下に輝きわたって―と賛辞を連ね、これ以上は畏れ多く筆をさし控える―と結ぶ。具体的な描写はない。そして一句。
〈あらたうと青葉若葉の日の光〉。ああ尊いことだ、青葉若葉に映る日の光は、神霊の荘厳そのもの―の意。日光の地名を読み込み、聖地の緑と光を切り取った表現はシャープだ。
だが、嫌みなくらい東照宮を持ち上げすぎな気もする。
「日記」によると芭蕉らは、参詣を前に浅草・清水寺で書いてもらった紹介状を持参し、人を介し拝観願を出した。ただ、幕府の絵師狩野探信一行も東照宮増修の打ち合わせで来ており、2時間ほど待たされている。芭蕉は、面白くないので「書くことを控えた」のではと、意地の悪い考えさえ浮かぶ。
しかし「黒羽芭蕉の館」(栃木県大田原市)の新井敦史学芸員(52)は「東照宮にまつられた東照大権現(徳川家康)は当時、天照大神に次ぐ威光を誇った。芭蕉の受け取り方はごく一般的」と言う。
素直に感じろということかと東照宮を訪れたのは平日、芭蕉らと同じ午後3時ごろだった。
観光地と別の顔
日光は、芭蕉の時代も今も一大観光地。そのシンボルが東照宮だ。混雑のピークはすぎただろうに、参道は観光客でにぎわっている。「日光の寺社」は世界遺産で、3月末には「平成の大改修」が終了したばかり。納得の人気だが、海外からの観光客が多いのに驚いた。周囲の半分くらいが外国人なのだ。
彼らと一緒に陽明門へ向かうと、傾いた日差しが、うっそうとした杉木立からチラチラとこぼれる。青葉若葉には早いが、自然の演出は見事だ。そして陽明門。随所に施された金箔(きんぱく)が、西日を受けきらめいていた。
満足感を感じつつ芭蕉の句碑を探す。多くの資料に「東照宮宝物館の近く」などと書かれているが、見つからない。真新しい宝物館で尋ねると、移転前の旧館の近くと教えられた。
旧館付近は、本殿周辺とはうって変わって人影はなく、ぽつんと「あらたうと―」の碑(小杉放菴書)があった。この森閑とした空気も、観光地とは別の日光なのだと思った。
「ほそ道」では参詣に続き、残雪の黒髪山(男体山)を望む場面が、旅のため髪をそり僧衣を着た曽良の決意を込めたような句とともに描かれる。これも人混みを離れ、ふと仰ぎ見た光景ではなかっただろうか。
〈剃(そ)り捨(すて)て黒髪山に衣更(ころもがえ)〉
(参考「奥の細道ハンドブック)
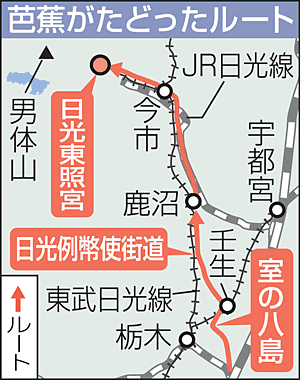
【 道標 】「予」と「芭蕉」重なる楽しさ
本欄ですでに記した通り「おくのほそ道」(以下「ほそ道」)は、単なる旅の「記録」ではなく「文学作品」です。
大枠では松尾芭蕉の旅路をなぞりながらも、事実から離れた記述が多くあります。それは芭蕉の紀行文観に基づいているものでもあります。
芭蕉が紀行文についての考えを披瀝(ひれき)したものとしては、「笈の小文」の中の記述が知られています。コンパクトに要約すると
〈1〉紀貫之の「土佐日記」をはじめ鴨長明、阿仏尼(あぶつに)の作品など、すでに紀行文には秀作があり、それらを凌駕(りょうが)することは困難〈2〉天気や見聞をただ並べてもつまらず、書くなら表現の新しさが求められる〈3〉それでも風景や感慨を記すことが風雅に通じると信じ、自分は書いている―。
芭蕉の本音を探れば、何とか先行作を超克しようと、事実の羅列とは一線を画した作品の実現を目指している、ということになるでしょう。
この紀行文観を前提にすれば、芭蕉の旅と紀行文とを混同することなく、作品そのものの特色や創作意図を探っていけばよい―ということになるでしょう。
しかし、そうはいっても、いつの間にか「ほそ道」の中の〈予=自分〉と、現実の〈芭蕉〉を同じ存在として読んでしまうことは十分にありえるし、文学作品を読む愉悦の一つは、そうした「虚実皮膜の間」をたゆたうことにあるのかもしれません。
もちろん、読んでいる自分が〈予〉に同化して旅の気分を味わうもよし、芭蕉を追い掛け「ほそ道」を片手に東北・北陸の旅に踏み出してみるのも楽しい。そうしたくなるだけの魅力が確かに「ほそ道」には備わっているはずです。(和洋女子大教授・佐藤勝明さん)
- 【旅の終わりに】俳人・長谷川櫂さん(下) かるみの先に心の安寧
- 【旅の終わりに】俳人・長谷川櫂さん(中) 宇宙の中に「不易流行」
- 【旅の終わりに】俳人・長谷川櫂さん(上) 『時の激流』どう生きるか
- 【 大垣 】<蛤のふたみにわかれ行秋ぞ> そして、また...旅が始まる
- 【 種の浜 】<浪の間や小貝にまじる萩の塵> 祭りの後...にじむ充実感
- 【金沢~山中温泉】<塚も動け我泣声は秋の風/今日よりや書付消さん笠の露>
- 【出雲崎~市振】<荒海や佐渡によこたふ天河><一家に遊女もねたり萩と月>
- 【 象潟 】<象潟や雨に西施がねぶの花> 憂いを帯びた『美女の趣』
- 【鶴岡~酒田】<暑き日を海にいれたり最上川> 鮮烈に残した夏の記憶
- 【 出羽三山 】<涼しさやほの三か月の羽黒山> 天空の世界へ一歩一歩