【白河・境の明神】<卯の花をかざしに関の晴着かな>ちりばめる和歌の記憶

1689(元禄2)年4月20日(陽暦6月7日)。江戸出発から23日目。朝、那須湯本をたった松尾芭蕉と河合曽良は、奥州街道の芦野宿(現那須町芦野)、その郊外の遊行柳を経由し同街道を北上した。
そして、上り坂を歩くこと10キロほどだろうか、たどり着いたのが「境の明神」。いわゆる「白河の関」、陸奥(みちのく)の入り口である。
ようやく、やって来た。大げさに言えば、ここで330年前の松尾芭蕉と、現在の旅人の感慨がシンクロする。
旅の覚悟固まる
「白河の関」は、「ほそ道」冒頭で書かれた通り、芭蕉を旅へと誘う陸奥のシンボルの一つ。そのあこがれの地、旅の本格的な出発点に立ち、芭蕉は「旅心定(たびごころさだま)りぬ」と記した。不安を抱えながら来たが、ここに来て旅の覚悟が固まったと、きっぱり言い切る。さすがである。
一方、記者は、遊行柳から目と鼻の先の国道294号を北へ進みながら「試行錯誤の取材も、ようやく本県入りか。やれやれ」と思う。俳聖の心境には及ばないものの、これも一つの旅心だろう。
だが、現代の陸奥の入り口はごく淡々と、緩い坂道の先に現れた。坂のピークの辺り、「ようこそ福島県」と書かれた福島・栃木県境の大きな標識は、「覚悟」とは無縁、どこか事務的だ。それも仕方ないのか。国道上では、自家用車やトラックが、日常的に行き過ぎていく。
県境の両側には、それぞれ神社が立ち、ともに「境の明神」と呼ばれる。芭蕉が訪れた当時から存在し、本県側の神社の境内には芭蕉の句碑も立つ。江戸時代の奥州街道と、陸奥の入り口の面影を今に伝える存在だ。
身を潜めて表現
ただ、頻繁な車の往来を見ていると、実は芭蕉も思ったほど興が乗らなかったのではと考えてしまう。なにしろこの場面、印象以上の風景描写はなく、芭蕉の句も記されていない。
「ほそ道」白河の関のくだりは、精密な時計のようだ。
今さらだが「白河の関」は、和歌の歌枕である。その言葉を触媒に、昔から多くの歌人が、都から遠く離れた未知の土地へ下る感慨をさまざまに詠んだ。芭蕉は、この数々の和歌の記憶を短い文章の中に、ぎっちり、かつスマートに詰め込んだ。
例えば「『いかで都へ』と便求(たよりもとめ)しも断(ことわり)也」(どうにかして都へ白河の関を越えたと伝えるつてを求めたのも道理である)は、平兼盛〈便りあらばいかで都へ告げやらむけふ白河の関は越ゆると〉(「拾遺集」)が念頭にある。
「秋風(あきかぜ)を耳に残し、紅葉(もみじ)を俤(おもかげ)にして、青葉の梢猶(こずえなお)あはれ也」の、秋の記憶は、能因〈都をば霞とともにたちしかど秋風ぞ吹く白川の関〉(「後拾遺集」)から想起された。
場面を締めくくる句〈卯(う)の花をかざしに関の晴着(はれぎ)かな〉も、能因に敬意を表し冠を正し衣装を改め関を越えたという白田の大夫(たゆう)国行の故事によるもの。ただ、これは曽良の句だ。
この記述について、元白河市文化財保護審議会長で元教師の金子誠三さん(92)は「古歌の聖地を表現するための文学的技巧」で、芭蕉が句を記さなかったのも「自分が主役として前に出てはだめだと、芭蕉は身を潜めた」と言う(「道標」参照)。そして「読者はどうしても、芭蕉は長旅で疲れていたのでは、などと考えてしまうんですよね」と嘆く。
では芭蕉は、ここで何を見たのか―と、県境をカメラのレンズ越しに見ていると、初夏の風に揺れる木々に気付いた。そう、風景についての数少ない描写の一つは「青葉の梢」だった。(原文、和歌の表記は佐藤勝明著「松尾芭蕉と奥の細道」による)
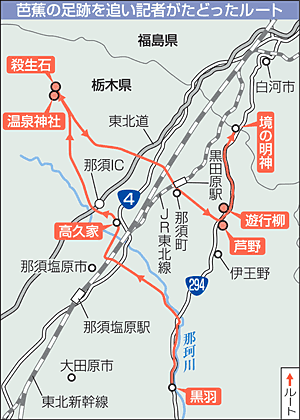
【 道標 】古歌の洪水の中で沈黙
「白河の関」にたどり着いた松尾芭蕉は、句を記しませんでした。これについて、歩き疲れていたなどの理由を推測する人は多くいます。しかし「おくのほそ道」は記録ではなく文学作品です。そこには文学的な意図があったと考えられます。
「ほそ道」は、全体が味わいの異なるパートで構成された「組曲」のような作品です。
白河の関と同様に有名な歌枕「松島」の場面は名文で迫力たっぷりに情景を描写しました。それもどことなく漢文調です。
白河の関の場面は、具体的な描写がありません。その代わり、古歌(昔の和歌)を素材につづられています。つまり松島も白河の関も、それぞれ異なる技巧が施されているのです。
逆に、松島と白河の関に共通する技巧が「絶景の前の沈黙」です。松島の場面でも芭蕉は句を記していません。素晴らしさに「言葉を失う」という文学的なポーズなのでしょう。
白河の関に絞れば「古歌の洪水の中での沈黙」です。俳人の山本健吉さんが言ったと思うのですが「白河は古歌の洪水である」という言葉があります。白河の関は昔から多くの歌人が詠み、和歌があふれている。そんな古歌の聖地だからこそ、芭蕉はこの場面で身を潜めました。
能楽やオペラに例えればこの場面の主役は芭蕉ではなく能因や平兼盛ら、いにしえの歌人たちです。彼らが次々と現れることで「古歌の洪水」を表現し、芭蕉は黒子に徹しました。
ただ、これでは俳諧の紀行文になりません。「諧」の意味は滑稽。最後は弟子曽良の句「卯(う)の花を」を置き「かるみ」「俳味」を出しました。これは松島も同じです。心憎い技巧が施されたのが白河の関の場面なのです。(インタビューを基に構成)(元白河市文化財保護審議会長・金子誠三さん)
- 【旅の終わりに】俳人・長谷川櫂さん(下) かるみの先に心の安寧
- 【旅の終わりに】俳人・長谷川櫂さん(中) 宇宙の中に「不易流行」
- 【旅の終わりに】俳人・長谷川櫂さん(上) 『時の激流』どう生きるか
- 【 大垣 】<蛤のふたみにわかれ行秋ぞ> そして、また...旅が始まる
- 【 種の浜 】<浪の間や小貝にまじる萩の塵> 祭りの後...にじむ充実感
- 【金沢~山中温泉】<塚も動け我泣声は秋の風/今日よりや書付消さん笠の露>
- 【出雲崎~市振】<荒海や佐渡によこたふ天河><一家に遊女もねたり萩と月>
- 【 象潟 】<象潟や雨に西施がねぶの花> 憂いを帯びた『美女の趣』
- 【鶴岡~酒田】<暑き日を海にいれたり最上川> 鮮烈に残した夏の記憶
- 【 出羽三山 】<涼しさやほの三か月の羽黒山> 天空の世界へ一歩一歩