【 川俣・小手姫と絹織りの町(上) 】 高品質「妖精の羽」世界舞う

「カッチャンカッチャン」「バッタンバッタン」。聞く人によって聞こえ方は異なるが、その正体は古くから養蚕と機織りが盛んな「絹の里・川俣」で代々受け継がれている織機の作業音だ。織機から聞こえる一定のリズムはいつも心地いい。
川俣の地に養蚕と機織りが伝わったのは、1000年以上も前のこと。「小手姫様」と呼ばれる女性が、川俣の地におりたち、養蚕に適した土地と見極めた。確たる文書は存在しないが、これが川俣絹文化の始まりとされている。
川俣町絹織物史によると、江戸時代初期ごろにはすでに川俣が絹の産地として知られていた。幕末や明治期には輸出用として重宝された川俣羽二重の高い技術を確立し、絹の里としての地位を築いていったという。
「昭和時代はバーバリーやディオールのスカーフの素材を町内で織っていたんだよ」。県織物同業会の会長で斎栄織物の斎藤泰行社長(73)は有名ブランドの名前を懐かしそうに挙げる。家族経営の店も含め、川俣町だけで約240社の機織り工場があり、出荷する数は違えど共同規格のものを作り合った最盛期のことだ。
ところが、石油危機による生糸価格の高騰や安価な輸入品の急増による売り上げ減少などで徐々にシャッターを下ろす業者が増加した。約240社あった機織り業者は現在1けたにまで激減。どんな道を通っても聞こえた機織り機の音は、次第に影を潜めていった。
◆再び注目の的
「機屋の景気と町の商店街の景気は比例する」。斎藤社長は続けざまに機織り業で栄えた町ならではの言葉を教えてくれた。機織り業者が所狭しとあったころ、同じように町内各地では多くの和菓子屋や美容室、八百屋なども看板を掲げていた。
当時の工場では2交代制により、休憩の間や仕事後は特に和菓子屋で甘味をとる前掛け姿の女性職員が目立った。機織り業者が町経済の潤滑油の役割を果たしていた。
町内の菓子屋「清水屋菓子舗」代表の渡辺邦子さん(75)は「とにかくにぎわっていたんだけどな」と回顧。絹織り業者の減少を受けて店じまいする同業者が増えた。今の街並みからは、当時の様子を想像するのは正直難しい。
「絹織り文化消滅か」。思わずそう言いそうになる現状だが、斎藤社長は「織物文化はそう簡単にはなくならない」ときっぱり。機織り業者が減ったことでかえって取引先や納入品のすみ分けが可能になったという。
斎栄織物が手掛ける世界一薄いシルク「妖精の羽(フェアリーフェザー)」を筆頭に、品質の高い製品を流通させる川俣の絹文化には再び注目が集まっている。「残った業者がそれぞれ得意分野で産地を守っていくだけだよ」と斎藤社長。小手姫様が伝えた「川俣シルク」は薄いが、なかなかしぶとい。
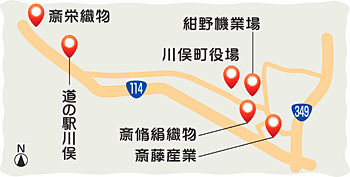
≫≫≫ ちょっと寄り道 ≪≪≪
【昔の機織り機や養蚕道具紹介】道の駅川俣施設内にあるかわまたおりもの展示館・からりこ館では、町内の機織り業者で使われていた昔の機織り機や養蚕道具が展示されているほか、1年に4、5回、絹に関する企画展が催される。機織りや、コースター織りなどの体験スペースも確保されており、昔ながらの絹織り文化を体験できる。月曜日は休み。

〔写真〕川俣町の機織り工場で使われていた機械が実際に見られるかわまたおりもの展示館・からりこ館
- 【 二本松・旧裏町 】 人と人...結んで元気に 社交場的な感覚がいい
- 【 いわき・植田の歩行者天国 】 継続が生んだ可能性 街支える力に
- 【 国見・あつかし歴史館 】 思い出の場所...『形変え』生きる学びや
- 【 猪苗代・中ノ沢温泉 】 流れ着いた男...温かい名湯と人情とりこに
- 【 いわきとアート(下) 】 多様さ生み育む『潮目』 本物を求めて
- 【 いわきとアート(上) 】 この店から始まった 病負けず創作活動
- 【 柳津・斎藤清晩年の地 】 求め続けた『古里の美』 消えない思い
- 【 須賀川・赤トリヰ 】 『夢の跡』また集う場に 笑顔あふれるよう
- 【 福島・土湯温泉(下) 】 荒波を越えて悠然と 温泉街のシンボル
- 【 福島・土湯温泉(上) 】 湯気の先に『職人の魂』 季節で味変化