【 福島・土湯温泉(上) 】 湯気の先に『職人の魂』 季節で味変化

1000年余りの歴史を誇る土湯温泉。巨大なこけしが四方を固める荒川大橋の上を歩くと、雪に覆われた吾妻山麓から吹き下ろす風に思わず首がすくむ。奥土湯に向けて橋を渡り切ると、店の片隅にあるせいろから湯気が立ち上るのが見えた。目にしただけで温まり、縮こまった体が緩むようだ。
せいろを置くのは、なかや菓子店。店主の陳野原弘治さん(76)は、冬にやってくる客たちに「土湯の湯は体が温まりやすく、冷めにくい。今が一番良さが分かる」と話し掛ける。店で商うのは旅館でのもてなしや、土産物に欠かすことができない温泉まんじゅうだ。
しっとりとした皮と、素材にこだわったあんには自信がある。見た目は何十年も変わりがないが、季節によって、微妙に味を変える。「あんは塩加減で決まる。冬は少しだけ多めに塩を打つと、濃厚さが出てくる」
◆喉越しを良く
店の歴史は、温泉街の変遷と重なり合う。大正時代に陳野原さんの祖父母が開いたなかやは、土湯の良水で作った豆腐を湯治でとう留する自炊客に売ったり、温泉宿に卸したりしていた。
まんじゅうが店に並ぶようになったのは、1965(昭和40)年。中学卒業後、東京の菓子店で修業した陳野原さんが豆腐の脇で作り始めた。高湯温泉と土湯峠を結ぶ磐梯吾妻スカイラインが59年に開通。街は湯治場から観光温泉地に様変わりしようとしていた。増えた県外からの客の土産物として、まんじゅうは人気を集めた。
当時は今と違って焼きまんじゅう。「焼き」から現在まで続く「蒸し」に変わったのは、温泉の客層の変化が理由だった。「昭和50年代になると、敬老会の団体旅行などが増えてきた。食べてもむせない、喉越しの良いものにしようと、蒸しまんじゅうにしたんだ」と陳野原さんは打ち明ける。
かつてのにぎわいを振り返る話し声は楽しげだが、陳野原さんの表情にはどこか寂しさも漂う。東日本大震災や東京電力福島第1原発事故の影響で、土湯温泉では旅館の廃業が相次ぎ、なかやの客も減った。「どんなお菓子を作れば好まれるのか。どこまでできるか分からないが、何かに挑戦しないといけない」。76歳の精気に自堕落なわが身を反省。また身が縮こまる気がした。
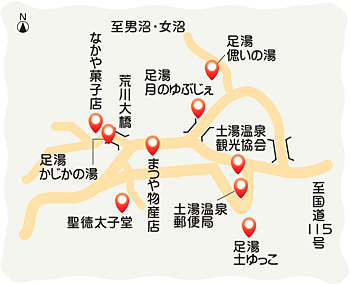
≫≫≫ ちょっと寄り道 ≪≪≪
【趣向異なる四つの足湯】土湯温泉街には「かじかの湯」「月のゆぶじぇ」「偲いの湯」「土ゆっこ」の4カ所の足湯があり、冬の街歩きで冷えた足元を温めるのに最適だ。すべてで源泉から引いた温泉をぜいたくに掛け流す。足湯はそれぞれ趣向が違い、自然石を生かした腰掛けがあったり、温泉街の景色が楽しめたりする。

〔写真〕荒川大橋のたもとにある足湯「かじかの湯」。足元をお湯に浸しながら、温泉街を眺めることができる
- 【 二本松・旧裏町 】 人と人...結んで元気に 社交場的な感覚がいい
- 【 いわき・植田の歩行者天国 】 継続が生んだ可能性 街支える力に
- 【 国見・あつかし歴史館 】 思い出の場所...『形変え』生きる学びや
- 【 猪苗代・中ノ沢温泉 】 流れ着いた男...温かい名湯と人情とりこに
- 【 いわきとアート(下) 】 多様さ生み育む『潮目』 本物を求めて
- 【 いわきとアート(上) 】 この店から始まった 病負けず創作活動
- 【 柳津・斎藤清晩年の地 】 求め続けた『古里の美』 消えない思い
- 【 須賀川・赤トリヰ 】 『夢の跡』また集う場に 笑顔あふれるよう
- 【 福島・土湯温泉(下) 】 荒波を越えて悠然と 温泉街のシンボル
- 【 福島・土湯温泉(上) 】 湯気の先に『職人の魂』 季節で味変化