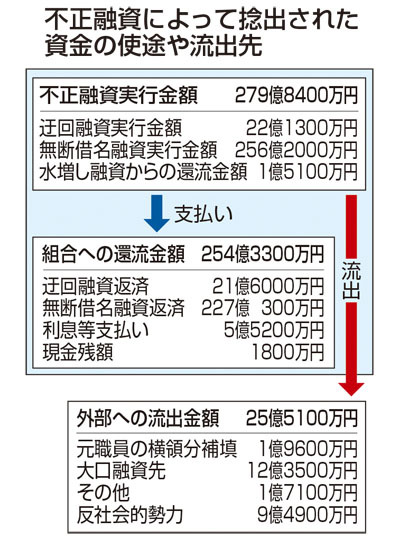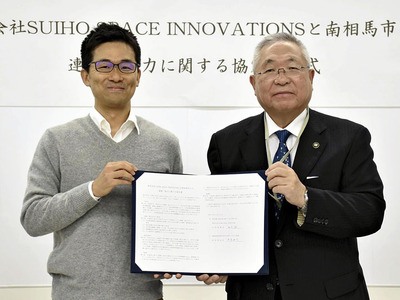不登校の子どもへの対応として最も重視されるべきは、早期に再び登校することではない。周囲が子どもたちの成長と自立を支える環境をしっかりと整えることだ。
文部科学省の問題行動・不登校調査によると、県内の小中学校で2024年度に30日以上欠席した不登校の児童生徒は前年度比27人増の4365人で、過去最多となった。中学校は90人減少したものの、小学校は117人増加した。
学校が把握した不登校の子どもからの相談で多かったのは、「生活リズムの不調」や「学校生活に対してやる気が出ない」でいずれも3割超だった。県教委の担当者は不登校の要因は多様化、複合化しているとした上で「原因は一人一人異なる。子ども本人にもはっきりとした原因は分かっていないことがある」と話す。
文科省は不登校は問題行動ではなく、子どもによっては休養が必要な場合があるとしている。学校や教育委員会、家庭は、子どもを追い詰めてしまわないよう原因の究明と解消を図りつつ、休養の継続を含め、子どもが必要としている支援を見極めることが大切だ。
不登校の子どもに対する支援策は民間のフリースクールを含め、多様化が進んでいる。県教委はモデル地区で行っていたオンライン教室の取り組みを全県に拡大し、登録した子どもは100人を超えた。通っていた学校に復帰した事例もあるという。棚倉町教委は今春、柔軟な教育課程を編成できる「不登校特例校」を開設し、不登校だった6人がこの校舎に通うようになった。
フリースクールや特例校には安心して通える子どももいれば、対面でなくオンラインならば人と交流できる子どももいる。家などで過ごすのが最適の場合もあるだろう。県教委などはさまざまな選択肢を充実させ、子どもの現状に即した学びや休養が得られるようにすることが重要だ。
不登校は中学校進学時や学年の変わり目など、環境が変化する時期に増える傾向がある。県教委は今春初めて、小学6年生を対象に学校生活に対する不安や悩みを聞き取るアンケート調査を行った。注意が必要とみられる子どもについては中学校と情報を共有し、スクールカウンセラーが面談するなど対応を強化している。
不登校を子どもの側の問題としてのみ捉えるのではなく、学校が子どもの実情に合った環境となっていない恐れにも目を向ける必要がある。調査を子どもの現状把握にとどまらず、学校の改善にも生かしてもらいたい。