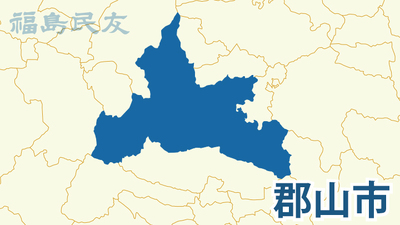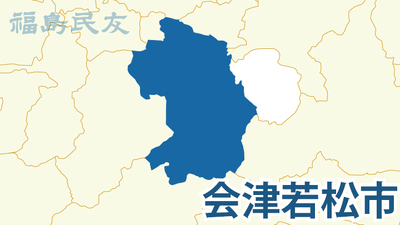患者本人だけでなく、周囲の人も正しい知識を身に付け、患者が安心して生活、治療できる社会を構築していく必要がある。
11月14日は「世界糖尿病デー」だ。国内では毎年、この日を含む1週間を「全国糖尿病週間」と定めており、今年は9~15日に啓発や予防の活動を展開している。
糖尿病は、血液中のブドウ糖を一定に保つホルモンのインスリンが十分に機能せず、血糖値が高くなる病気だ。放置していると、血管が傷つくなどして、心臓病や失明などの合併症を引き起こす。
種類は大きく二つに分かれる。1型糖尿病は免疫反応の異常が原因と考えられ、子どもの頃の発症が多いとされる。毎日の注射でインスリンを投与する必要がある。2型糖尿病は遺伝のほか、運動不足や肥満といった生活習慣が影響し、インスリンが出にくくなったり、働きにくくなったりする。
国内では糖尿病患者は約1000万人と推計され、うち9割超が2型糖尿病とみられる。かつては発症すると完治が難しい難病とされたが、最近は薬、治療法が進歩しており、健康な人とほぼ同じように生活することができる。ただ初期段階では自覚症状があまりない。健康診断などで早期に発見し、適切な治療を行うことが大切だ。
国の2024年人口動態統計によると、本県の死因別死亡率(人口10万人当たりの死亡数)で、糖尿病は17.7人と、がんや心疾患などと比べ死亡率は低いものの、都道府県別ではワースト6位だ。
糖尿病は代表的な生活習慣病であり、食生活の乱れや運動不足、喫煙、ストレスなどと深く関係している。本県は食塩摂取量や喫煙率、肥満者の割合など生活習慣に関する指標が悪いことも死亡率の高さに影響している恐れがある。
糖尿病の発症や重症化を防ぐため、日頃から生活習慣に細心の注意を払わなければならない。医師などのアドバイスを受け、必要な改善を図ることが求められる。
患者や医師らでつくる日本糖尿病協会などは2年前、糖尿病の呼称を英語名の「ダイアベティス」に変更する案を示した。患者から病名に「尿」が含まれることへの不快感や、不潔、怠惰な生活などの負のイメージにつながるとの意見が上がっていたためだ。
患者が前向きに治療に取り組むのを避けたり、周囲に病気を隠したりするケースもあるという。実際は尿に糖が出るのは症状の一つに過ぎない。誤解や偏見から適切な治療を阻むことがあってはならず、呼称変更でこうした環境を変えていくことが重要だ。