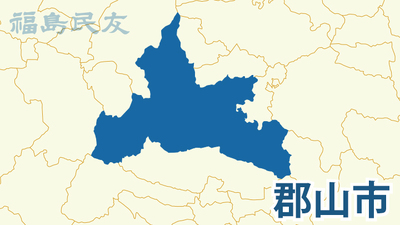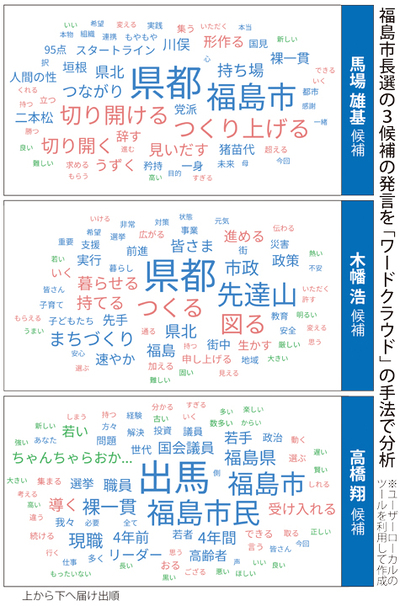本県は東日本大震災を経験したが、その教訓を踏まえた防災・減災対策は十分に講じられているだろうか。海溝型の地震による津波や台風による浸水など、再び大災害に遭うリスクはゼロではない。平常時から、災害に強い地区づくりを進めておくことが重要だ。
震災の教訓の一つは、大規模災害時には「公助」に限界が生じるということだ。そこで「自助」と「共助」の力を高めようと、2013年の災害対策基本法改正で、住民が自治会単位などで災害に備える「地区防災計画」を作ることが定められた。ただ、策定は地区の自主性に任せているため、県内は19市町村54地区にとどまる。
計画については、内閣府のガイドブックで一定の基準が示されている。具体的には、地震など過去の災害の事例を踏まえ、平常時の訓練や備蓄の方法、災害時の情報共有や避難の判断をどうするかなどを書き込む。18年の西日本豪雨では、計画に基づき迅速に避難し犠牲者を出さなかった地区があるなど、効果が確認されている。
山口大大学院の滝本浩一准教授(防災・まちづくり)は、「災害で自助ができずに多くの住民が亡くなれば、その後の共助はできない」と指摘する。そのため「地区には、ごみ出しや防犯など何らかの人の結び付きがある。その力を生かし、地区単位で災害前に家具の転倒防止などの自助の備えを促すことが必要。計画作りはそのきっかけになる」と訴える。県や市町村は、改めて計画作りの必要性を周知してもらいたい。
しかし、住民が一から作るにはハードルが高いのも実情だ。県は、防災まち歩きや災害図上訓練(DIG)などを交えた1回2時間程度の研修を3回ほど受講すれば、計画の基礎を作ることができる講座を準備している。自治会などは、行政や防災関係の専門家らの支援を得ながら、計画作りに取り組んでほしい。
災害時の対応を巡っては、市町村に対し高齢者ら要支援者それぞれに「個別避難計画」を作ることが求められている。だが、行政の人手不足などから、県内に約14万人の対象者がいるにもかかわらず、約13%に当たる1万7千人超しか計画ができていない。
地区防災計画を策定する目的の一つには、自治会の中で助けが必要な人がどこにいるのかを把握して、周囲の力で安全に避難してもらうことがある。その作業は、個別避難計画作りと共通する部分がある。市町村が防災計画を作る地区と連携し、個別避難計画の策定を進めていくことも必要だ。