「ゆがみの構図」編へ識者の意見【番外編 下】富田愛さん・ビーンズふくしま・みんなの家@ふくしま事業長
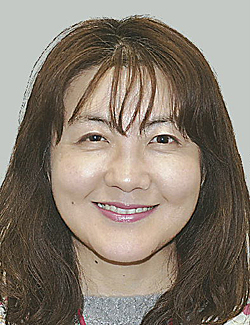
富田愛さん
◆富田愛さん(自主避難者を継続支援)
どんな選択も尊重を
東日本大震災からまもなく丸5年になるが、自主避難者の選択の難しさは、時がたつほど深まっているように思う。親の仕事や子どもの進学など、それぞれの家庭で事情が異なってきているためだ。
自主避難者一人一人と話をすると「日々の生活をどう乗り越えていくか」に一生懸命な人がほとんど。家族のことを第一に考えている人が多い。帰還するか、避難を続けるかは一人の親が抱え込むには大きすぎる問題だ。ある母親は「いっそ誰かが決めてくれれば」と言っていた。だからどんな選択をしても、それを尊重することが大切だ。
「帰還する人」「避難を続ける人」「不安を抱えながら福島で生活する人」それぞれの人の思いと向き合っていく必要がある。子育てするママは賢い。寄り添って支えてくれる人がいれば、悲観だけでなく、福島ならではの子育ての知見が集まるのではないか。
来年3月、自主避難者への住宅補助が打ち切られるが、これに対しては冷静な受け止めが多い。不安を抱えながらも、経済的な理由で帰還せざるを得ないという人も出てくる。それぞれが生活再建できるよう支援を続けていく必要がある。
(2016年2月16日付掲載)
- 【復興の道標・放射線教育】ママ考案「○×テスト」 相馬・中村二中で初授業
- 【復興の道標・放射線教育】学び続ける風土つくる 意欲に応える方策を
- 【復興の道標・放射線教育】教える側の意識が変化 福島モデル確立へ
- 【復興の道標・放射線教育】「なぜ学ぶか」が出発点 理解し伝える力に
- 【復興の道標・放射線教育】「放射能うつる」の誤解 学校外の連携模索
- 【復興の道標・放射線教育】安全性伝える知識必要 相馬農高生が実感
- 【復興の道標・放射線教育】子どもが学び家庭へ 測定検査で実践的活動
- 【復興の道標・識者の意見】立命館大准教授・開沼博氏 寝た子を起こすべき
- 【復興の道標・識者の意見】県国際交流員・ナオミオオヤ氏 ALTが情報発信
- 【復興の道標・番外編】理不尽に心痛める福島県民 教育・行政対応求める