被災9市町村「風化」を実感 大熊「震災経験の職員5割以下」
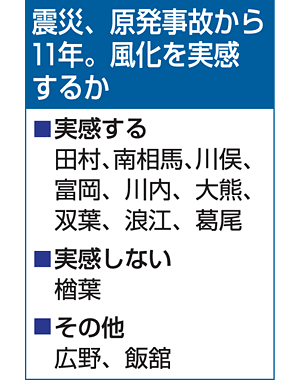
東日本大震災、東京電力福島第1原発事故から11日で丸11年を迎える中、避難指示が出るなどした12市町村のうち9市町村が「風化」を実感していることが福島民友新聞社のアンケートで分かった。本年度から「第2期復興・創生期間」に入るなど復旧・復興が着実に進む一方、各市町村とも教訓の「伝承」を課題に挙げた。
風化を「実感する」と回答したのは田村、南相馬、川俣、富岡、川内、大熊、双葉、浪江、葛尾の9市町村。唯一全町避難が続く双葉町の伊沢史朗町長は「いまだに全町避難している自治体があることを知らない人が多い」と訴え、「町自らがこの状況を発信していく」と強調した。南相馬市の門馬和夫市長は「報道などで取り上げられる機会が減り、復旧・復興が既に完了していると受け止められる」と懸念を示した。
各市町村は伝承施設や記録誌、語り部の確保など伝承に向けた取り組みを進めているが、大熊町の吉田淳町長は「震災を経験した職員が5割以下。職員へ伝えることも大事」と課題を指摘。浪江町の吉田数博町長は「当時の状況や町民の苦悩を繰り返し報道することは、マイナスイメージを増幅し『風評』を助長してしまう」と風評と風化のはざまに立つ苦悩を明かした。
風化の「実感はない」としたのは楢葉町のみだが、あくまで「町内で」との立場だ。松本幸英町長は町外でも「震災があった地域として認識し続けられるよう訪問者の確保に取り組む」とした。
「その他」は2町村。広野町の遠藤智町長は「震災を知らない新たな世代に語り継いでいくことが重要」、飯舘村の杉岡誠村長は「次世代の『問い』に対応する伝承方法が必要」と、いずれも将来世代への伝承が大切との考えだ。
内堀雅雄知事は7日の定例記者会見で、経年による風化とともに「実際に現場に行き、生で訴える機会が新型コロナウイルス禍で失われており、大きなマイナス」と指摘。「リアルでの情報発信と感染対策を両立しながら、風化抑制に努めていく」と風化防止に向けた取り組みを進める考えを示した。
移住・人口増、相談窓口設置や情報発信
原発事故による避難指示などで依然として3万3000人を超える県民が避難生活を送る中、各市町村では住民の帰還はもちろん、移住促進などによる人口増に向けた施策が不可欠だ。福島民友新聞社はアンケートで、各市町村の取り組みについても聞いた。
大熊町は今春に移住定住支援センター、葛尾村は新年度に移住支援センターを設立する予定で、移住定住を進める考え。大熊町の吉田淳町長は「仕事や住まいの相談窓口を開設し、情報発信を強化する」、葛尾村の篠木弘村長は「産業誘致による雇用の創出で受け皿づくりを進めたい」とした。
田村市は東京・渋谷区に「東京リクルートセンター」、市内に「田村サポートセンター」を開設、首都圏の移住検討者の掘り起こしを図る。楢葉町は「まかない付きシェアハウス」の整備を進めている。
また、広野町の遠藤智町長は廃炉や復興を担う人材育成も念頭に「被災地に特化した『実学の場』を提供し、若者を迎え入れたい」との考えを示した。このほか、各自治体とも若い世代の帰還・移住を見据えて子育て支援の充実に取り組んでいる。
- 美里で耕す第二の人生 浪江から避難、元SEの農家「恩返しを」
- 星降る農園、浪江のスターに 元外交官・高橋さん、移住し奔走
- 葛尾に国内最大エビ養殖場 7社出資のHANERU社、24年度出荷へ
- 白河・小峰城の北西エリア開放 石垣修復、4月9日に11年ぶり
- 【震災11年・備える力】災害語り部/記憶継承、若者の手で
- 豊間の伝承...防災紙芝居に いわきの団体制作、経験を次世代へ
- 郡山市、4小学校に「非常用備蓄品」配布 フードロスを削減へ
- 【震災11年・備える力】コロナ下/感染恐れ避難ためらわぬように
- 【震災11年・備える力】個別避難計画/「要支援者」を守る命綱
- 【震災11年・備える力】夜間避難/災害は時間を選ばない