相手の心の扉を開ける 東北福祉大教授・塩野悦子さんに聞く
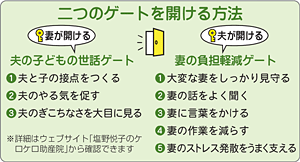
子育てが始まり、夫婦で協力したいのに、うまくいかない―。そんなときにどうすればいいのか、助産学が専門で、「産後クライシス」の予防プログラムを開発し妊娠中の両親教室で実践している東北福祉大健康科学部保健看護学科教授の塩野悦子さんに、産後クライシスが起きる仕組みや、予防法について聞きました。
Q・「産後クライシス」とは?
「"出産後早期の夫婦間のすれ違い"のことを指しますが、私は『妊娠中は夫婦2人で同じ道を歩んでいると思っていたのに、子どもとの生活が始まると、別々の道を歩んでいるような感覚になること』と説明しています。『父親の育児への関わり方に対する母親の不満』が一般的ですが、私の定義には『父親側が抱える、育児に対する疎外感や無力感』も含まれます」
Q・なぜ起こる?
「『父親と母親の違い』が関係しています。生物的にも心理的にも先に親になる母親は子どもの世話の負担が大きく、夫に対して不公平感を抱きやすい。一方、父親は母子の退院後や里帰り後から子どもとの生活が始まりますが、子どもをうまくあやせず疎外感を抱いたり、慣れない手つきを妻から駄目出しされ萎縮(いしゅく)したり。父親としての出番が予想より少ない状況に出くわします。この違いがクライシス(危機的状況)を生みます」
Q・防ぐ方法は?
「産後クライシスはどの夫婦にも起こる当たり前のことですが、程度を小さくすることはできます。私は、初めて子育てをしている夫婦は『父親と母親の違い』を巡って二つのゲート(心の扉)を開け閉めしている、と考えています。このゲートを開けることが産後クライシスの予防につながります」
Q・二つのゲートとは?
「一つ目は『夫の子どもの世話ゲート』で、鍵を持つ妻がゲートを開けると、子どもの世話に対する夫の意欲が増し、閉めればそがれる。うまく開けるには、妻が〈1〉夫と子の接点をつくる〈2〉夫のやる気を促す〈3〉夫のぎこちなさを大目に見る―こと。特に『さすが!』『すごい!』と褒めると効果的です。もう一つは『妻の負担軽減ゲート』。開けるためには鍵を持つ夫が〈1〉大変な妻を見守る〈2〉妻の話をよく聞く〈3〉妻に言葉をかける〈4〉妻の作業を減らす〈5〉妻のストレス発散を支える―ことが必要です。夫が『妻の負担軽減ゲート』を開ければ、妻も『夫の子どもの世話ゲート』を開けやすくなります。このゲートは自然と閉まるので、意図的に開けることがポイントです」
Q・苦しい人どうすればいい?
「子育て中の夫婦は、すれ違いと解決を繰り返していくもの。すれ違うたびに一本道に戻せばいいんです。『二つのゲート』を参考に、夫婦が自分の行動を見直し、対話することが大切です」
Q・周りの人ができることは?
「ゲートの開け閉めは誰にでもできます。例えば、夫の母親(孫の祖母)が息子を褒めて子育てへのやる気を促せば『夫の子どもの世話ゲート』を開けるサポートになります。妻の母親が出産した娘にねぎらいの言葉をかけたり、話をよく聞いたりすれば『妻の負担軽減ゲート』を開けられます」
◇
塩野悦子(しおの・えつこ)東北福祉大健康科学部保健看護学科教授。仙台市出身。東京医科歯科大大学院看護学博士課程修了。専門は助産学。宮城県助産師会会長。66歳。