| >>> 原発災害・「復興」の影TOP
|
|
|
“放射線と向き合う” 固執すると別のリスクが高まる恐れも
|

|
|
卒業式後、同級生と談笑する渡辺さん(左)。3年間の思い出を胸に4月から社会人となる=1日、川俣高
|
「県産の野菜に『不検出』と表示があれば(放射性物質を)気には掛けなくなった」。3人の子を持ついわき市の主婦伊谷千江美(33)は最近、原発事故後は避けていた県産品を購入するようになった。伊谷は、子どもが近所の公園で遊ぶときも、空間放射線量が年間積算線量1ミリシーベルトを下回る計算となる毎時0.2マイクロシーベルト程度なら「自分の中で許している」と話す。
産業技術総合研究所フェローの中西準子(75)=環境リスク学=は「国は原発事故前から、日常生活で発がん性物質などのリスクが常にありゼロではないことを隠してきたため、日本人はリスクの捉え方に慣れていない」と指摘する。
「絶対安全の境ない」
放射線の影響によってがんで死亡する割合は100ミリシーベルトで0.5%上昇するとされる。しかし、中西は「専門家が『年間100ミリシーベルト以下の影響はよく分からない』と言うことが住民の誤解を招く」と指摘する。発がん性物質は、この量以下なら絶対に安全という境目はなく、微少な発がん性物質には微少な発がんリスクが推計上はあるということになる。「リスクの数値を詳しく知ることは大事。ただ、ごく小さいリスクにこだわり過ぎると、むしろ別のリスクが高まる恐れもある」
胸の内に不安が残る
飯舘村の全村避難が決まった際、2011(平成23)年5月に開かれた東京電力の説明会で「将来結婚したとき、被ばくして子どもが産めなくなったら補償してくれますか」と質問した飯舘村の渡辺菜央(18)=川俣高3年=は「子どもにしか分からない不安だから聞いた」と当時を振り返る。川俣町に避難した渡辺は借り上げ住宅から高校に通い、学校の除染、屋外活動の再開などを経る中で不安はだいぶ薄れてきた。4月からは避難先から通えるJAで働く。「放射線の影響は分からないが家族と離れるのは放射線より不安だった」。もちろん渡辺の胸の内で放射線への不安はまだゼロではない。
それでも漠然と思い描く将来には、結婚し、この地で子どもを産む自分の姿がある。「親がいて、自分と夫がいて、子どもがいる暮らし。自分は3世代同居で育ったから、それがいい」(文中敬称略)=「身を守る」おわり
(2014年3月10日 福島民友ニュース)
|
|
( 2014年3月10日付・福島民友新聞掲載 )
|
|
|
|
民友携帯サイト
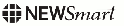
右のコードを読み取り、表示されたURLでアクセスできます。
|
 |
|
|