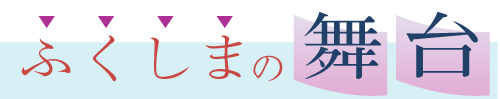 |
|
作家・宮本百合子「貧しき人々の群」
(郡山市)
|
|
開拓の歴史刻む開成山公園
|
|

|
|
開成山公園内にある彫刻「開拓者の群像」。宮本百合子の文学の碑などとともに公園の象徴となっている
|
こいのぼりがたなびく郡山市・開成山公園。市中心部の市民の憩いの場は、同市の発展の基礎を築いた安積開拓の発祥の地でもある。かんがい用の池が今に残る五十鈴湖、開拓初期に植えられた桜の古木は開拓にかかわった多くの人々の苦労や栄枯を見つめ、大事業の歴史を今に伝える。
「(入植者は)幸福を夢想しながら、故国を捨てて集まって来た。けれども、ここでも哀れな彼等は、思うような成功ができないばかりか、(中略)彼等は今も昔も相変わらず貧しい…」
作家宮本百合子は、学校の休みに東京から祖父の家のある郡山をたびたび訪れた。開拓村の貧しい小作人の生活を目の当たりにし、その姿を小説「貧しき人々の群」に描いた。
1872(明治5)年、県令安場保和と宮本の祖父の典事中條政恒は開成山の開拓(大槻原開拓)を決断、地元の富裕者による開成社の結成を促し、同社による開拓が始まる。これが後に、士族授産などを目的とした明治政府初の国家的大事業・国営安積開拓につながる。猪苗代湖から安積疏水が引かれ「500戸移住」の士族開墾が始まる。安積疏水は豊かな水と電気をもたらし郡山の発展を支えた。しかしその一方、多くの入植者は開墾地の生産性の低さから貧困にあえぎ、小作農に転落したという。
文芸評論家でこおりやま文学の森資料館初代館長の塩谷郁夫さんは「祖父の理想を理解する一方で、貧しい人々をどうすればいいのか。その矛盾の解決が、宮本文学の一貫したテーマとなった」と作品の意義を語る。
|
| >>>
MAP |
|
|
開成山公園 開成社が造ったかんがい用池の跡。同社が植えた桜や安積開拓をモチーフにした彫刻「開拓者の群像」も。開拓者の心のよりどころとして建立された伊勢神宮唯一の分社開成山大神宮は公園の西隣にある。
▽問い合わせ=郡山市観光物産課(電話024・924・2621) |
|
【 5 】
2008年5月1日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
( 文・金沢茂 写真・一ノ瀬澄雄 )
|