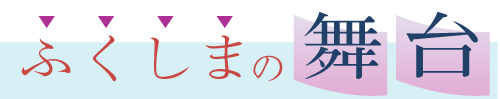 |
|
芭蕉ゆかりの信夫文知摺
(福島市)
|
|
数々の伝説を残す歌枕の地
|
|

|
|
緑に囲まれた境内に残る芭蕉の句碑。芭蕉が来福して105年後、京都の俳人・丈左房が追恩の句会を記念し建立した
|
平安時代の古今和歌集に詠まれた歌枕の地で、平安貴族と地元の娘との悲恋物語や石の伝説など数々の言い伝えを残す信夫文知摺は、後世の文人の創作意欲をかき立てた。
伝説は、娘が都に戻った貴族に会いたい一心で文知摺観音に百日参りの願をかけたところ、一瞬だが文知摺石に貴族の面影が映ったと伝えられている。
俳聖・松尾芭蕉は1689年(元禄2)年、旧暦の5月、旅の途中にこの地に立ち寄り、「奥の細道」に「早苗とる 手もとや昔 しのぶ摺」と詠んだ。
また、「石は近くの山の上にあったが、想い人の姿を映すというので当時の女性たちが収穫前の麦の穂を取って石を磨くことが重なり、それに腹を立てた農民が石を投げ落とし、上下が逆さまになって現在の地に落ち着いたと聞いた」という記述も残している。
信夫文知摺を管理する安洞院住職の横山俊邦さんは「芭蕉はすべてを調べた上で訪れていた」という。「平安時代、夫は防人として中央にとられ、生活を切り盛りするのは残された女性たちだった。当時の女性の心の支えが伝説の石であり、観音信仰だった。芭蕉は女性の心情を田植えする手元に重ね合わせたのではないか」と話す。
芭蕉を尊敬する正岡子規もまた約200年後の1893(明治26)年7月、ここを訪れ「涼しさの 昔をかたれ 忍ぶずり」と句を残した。
新緑の木立に囲まれた境内は、当時に思いをはせるのに十分な静けさが広がり、訪れる人を伝説の世界に誘っている。
|
| >>>
MAP |
|
|
信夫文知摺 境内には県重文で東北唯一とされる多宝塔遺構や夜泣き石、人肌石と呼ばれる伝説の石がある。もちずり美術資料館には芭蕉や子規の真筆を展示している。
▽問い合わせ=曹洞宗香沢山安洞院(電話024・534・0939)。 |
|
【 6 】
2008年5月8日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
(
文・佐藤綾 写真・矢内靖史 )
|