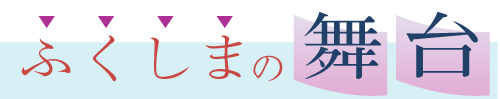 |
|
小手姫伝説の大清水
(川俣町)
|
|
「絹の里」の織り姫最期の地
|
|

|
|
川俣町中央公園に立つ小手姫像。小手姫伝説が息づく「絹の里」を静かに見守っている
|
古くから絹織物の産地として栄えた川俣町。大清水は、その「絹の里」に機織り、養蚕の技法を伝えたという小手姫の最期の地とされる。小手姫が世を儚(はかな)み身を投げたという池には、今もひっそりと清水がわき続ける。
全国の織物の産地には数多くの織り姫伝説が残る。その一つ、小手姫伝説にも諸説ある。現在は第32代崇峻天皇の妃(きさき)とする説が広く知られる。「『信達二郡村史』付録・甲集之上巻」(1902年)によれば、小手姫は勢力争いに敗れ都を追われた息子・蜂子皇子を追い川俣の地にたどり着いた。そして70歳までとどまり、機織りの技術を伝え、絹織物の礎を築いたとされる。
川俣周辺の逸話などを集めた「小手風土記」(1788年)には「勅ありて大和国より庄司峯能と云ひし人、ひとりの娘小手姫をともなへ謠々陸奥に下り、桑を植え蚕を飼しめ女工を教しむる」との記述がある。
同町在住の県文化財保護指導員高橋圭次さんは「機織りが中央から伝わった経緯が徐々に神格化され、小手姫伝説に発展した可能性がある」と話す。
伝説では、川俣に機織りを広めた小手姫はその後、ついに息子と会うことはできず、大清水に身を投げ生涯を閉じた。その後、大清水には住民の手で祠(ほこら)が造られ、1910(明治43)年には織姫神社として祀(まつ)られた。
小手姫と大清水は今では町の象徴となり、中心街を見下ろす中央公園に建立された像が、伝説息づく町を静かに見守っている。
|
| >>>
MAP |
|
|
小手姫伝説の大清水 大小2つの池を持つ町指定名勝。近くに大清水古墳群などの遺跡もある。2つの池の間には明治中期に建設され、その後、移設された町有形文化財の旧壁沢川石橋も架かる。
▽問い合わせ=川俣町役場産業課(電話024・566・2111) |
|
【 8 】
2008年5月22日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
(
文・白坂俊和 写真・永山能久 )
|