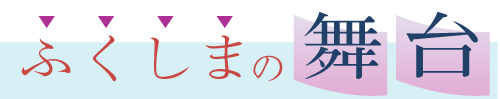 |
|
「荒城の月」と鶴ケ城
(会津若松市)
|
|
感銘受けた土井晩翠が作詞
|
|

|
|
鶴ケ城の一角にある「荒城の月碑」が、歌詞発祥の地であることを今に伝える
|
満々と水をたたえるお堀を見ながら新緑の間を抜けると、見上げるような石垣が現れた。その石垣はちょうど140年前に繰り広げられた戊辰戦争を現代に伝えている。
本紙の「福島遺産 百選」にも選ばれた鶴ケ城は会津若松市のシンボルとして市民や観光客に親しまれている。その天守閣がある一角に「荒城の月碑」がある。
「荒城の月」は東京音楽学校の依頼を受けた土井晩翠が1898(明治31)年、作詞した日本を代表する唱歌。土井が旧制第二高等学校在学中に訪れ、戊辰の戦火で荒れ果てた姿に感銘を受けた鶴ケ城に、出身地である仙台市の青葉城のイメージを重ね作詞したといわれる。
終戦直後の1946年、会津若松市で開かれた音楽祭に招かれた土井は「依頼されてまず思い浮かべたのは修学旅行で訪れた鶴ケ城の姿だった」と語り、会場はあまりの驚きにしばらく静まり返ったと伝えられる。「荒城の月」のモチーフが鶴ケ城という土井の言葉を受け、地元の有志が翌47年に土井直筆の「荒城の月碑」を鶴ケ城に建立した。
今、同市では毎年、幼稚園、学校、一般の音楽団体が一堂に会する「荒城の月市民音楽祭」が開かれている。今年で9回を数えた。発起人の一人、同市の高橋市郎さん(79)は「若い世代には『荒城の月』そのものを知らない人が増えている。鶴ケ城といえば戊辰戦争だが、名曲のモチーフになるような文化的な歴史もあることを後世に語り継ぎたい」と静かに語る。
|
| >>>
MAP |
|
|
鶴ケ城 戊辰戦争後に取り壊された天守閣は1965(昭和40)年に市民からの寄付などによって再建された。歌碑は天守閣から南東方向の、茶室「茶室麟閣」の奥にある。
▽問い合わせ=会津若松市観光公社(電話0242・27・4005) |
|
【 9 】
2008年5月29日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
(
文・田村祐一 写真・吉田義広 )
|