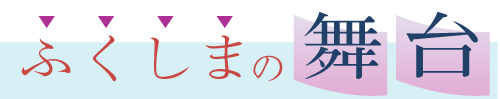 |
|
医王寺 乙和の椿
(福島市)
|
|
芭蕉も涙 悲しい物語が由来
|
|

|
|
大河ドラマ「義経」にも登場する、源義経の家来佐藤一族の菩提寺としても有名な医王寺。観光ルートの一つとして多くの観光客が訪れる
|
源義経の忠臣佐藤継信、忠信兄弟の菩提(ぼだい)寺として知られる福島市飯坂町の医王寺。境内の奥にある2人の墓標の傍らには、父基治、母乙和の墓とともに、花が開かずつぼみのまま落ちてしまう一本のツバキがある。「乙和の椿(つばき)」と呼ばれるこの古木の名は、松尾芭蕉も涙した悲しい物語が由来となっている。
奥州藤原氏とのつながりが深かった基治は、義経の源平合戦に際し、継信、忠信兄弟を派遣。2人は義経のもとで活躍したが、継信は屋島の合戦で、忠信も京都で主君の身代わりとなって戦死した。
最愛の息子2人を相次いで亡くし乙和は悲しみに暮れていたが、そんな義母をどうにか慰めようと継信の妻若桜と忠信の妻楓は自らの悲しみをこらえ夫の甲冑(かっちゅう)をまとい「継信、忠信、ただいま凱旋(がいせん)しました!」と乙和の前に現れたという。
1689(元禄2)年、「奥の細道」の行脚で寺を訪れた芭蕉はこの逸話に触れ「中にも2人の嫁がしるし先づあはれなり、女なれどもかひがひしき名の世に聞えつるものかなと袂(たもと)をぬらしぬ」との記述を残し「笈(おい)も太刀も5月に飾れ紙幟(のぼり)」と詠んだ。
1995(平成7)年の「ふくしま国体」では、この物語を下地にした県民創作オペラ「乙和の椿」が上演され、多くの人に感動を与えた。境内の奥にひっそりとたたずむ咲かずのツバキは、わが子を思う母親の愛情と家族のきずなの深さを今も静かに伝えている。
|
| >>>
MAP |
|
|
医王寺 佐藤一族の菩提寺。平泉に向かう義経一行が立ち寄り継信、忠信の遺髪を納めたといわれ、兄弟の鐙(あぶみ)や弁慶の笈(おい)、義経が基治に贈った直垂(ひたたれ)などが残る。
▽問い合わせ=瑠璃光山医王寺(電話024・542・3797) |
|
【 11 】
2008年6月12日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
(
文・小椋秀一 写真・矢内靖史 )
|