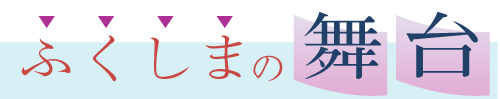 |
|
岩瀬牧場
(鏡石町)
|
|
唱歌になったのどかな風景
|
|

|
|
「牧場の朝」の歌詞にも登場する鏡石町指定文化財の「鐘」や牛の血統書などが展示されている歴史資料館内
|
「ただ一面に立ちこめた 牧場の朝の霧の海」で始まる旧文部省唱歌「牧場の朝」。多くの人に親しまれるメロディーと歌詞からは、さわやかな朝の風景が浮かび上がる。
唱歌の舞台、鏡石町の岩瀬牧場では今、緑の中で牛の群れがのんびり草をはむ。その向こうには、古びたサイロが見える。
同牧場は、明治天皇の東北巡行をきっかけに宮内庁直営の開墾地所として開設。1907(明治40)年にはオランダからホルスタインの種牛13頭と農機具を導入、日本初の西洋式牧場となった。
場内の歴史資料館には伝統を伝える品々が並び、その一点がオランダから友好の印として贈られた鐘(町文化財)。これが「牧場の朝」で「鐘が鳴る鳴る、かんかんと」と歌われた鐘だという。
そんな挿話にひかれてか牧場には多くの観光客が訪れる。しかし、この人気も名曲にまつわる謎が解けてからのことだという。
「牧場の朝」は昭和初期、「新訂尋常小学唱歌(4)」に発表され、船橋栄吉東京音楽学校教授の作曲と知られながらも、長く作詞者不詳だった。この謎を解いたのが鏡石町の医師だった故最上寛さん。「岩瀬牧場がモデル」との「うわさ」を基に昭和30年代後半から約10年調査を重ね、新聞記者で随筆家だった杉村楚人冠が同牧場を訪れた体験を基に作詞したことを突き止めた。
元場長の大泉清さん(72)は「牧場の歴史を学んでいただければ」と牧場に生きづくロマンに胸を張った。
|
| >>>
MAP |
|
|
岩瀬牧場 宮内庁直営の開墾地所として開設。現在は民営で、30ヘクタールの広大な園内では、動物との触れ合いや収穫、バター作りなどが体験できる施設がある。
▽問い合わせ=岩瀬牧場(電話0248・62・6789) |
|
【14 】
2008年7月3日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
(
文・玉手忠平 写真・永山能久)
|