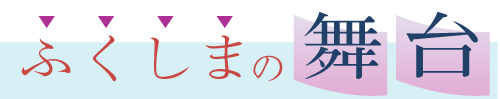 |
|
稚児舞台
(二本松市)
|
|
阿武隈川急流の奇岩怪石
|
|

|
|
伝説の稚児舞台は、稚児桜と呼ばれるユキヤナギの群生地ともなっている
|
阿武隈川の急流に囲まれ、西側の高台から見ると島のようにも見える島山。
島山の下流に奇岩怪石が千変万化の景観を織り成す渓谷があり、稚児舞台と呼ばれる。稚児舞台は、源義家に稚児の舞を見せようとした場所とされ、悲話が残る。
奥州征伐に来た源義家の大軍が阿武隈川を挟んで奥州の豪族安倍貞任の軍勢と数10日も対峙(たいじ)し、弓矢の合戦を繰り返していた。1055(天喜3)年春、双方の兵が疲れ果てたある日、東岸の源氏勢が「奥州の豪族といえども、舞を舞う子女は一人もおるまい」と安倍勢をはやし立てた。
安倍貞任は「それまで言われては一門の恥」と激怒し、2人の美女を稚児姿に仕立て、大きな岩を舞台に舞を舞わせた。2人は花に遊ぶチョウのように優雅に舞ったという。このときは、川の瀬も群れ飛ぶ鳥の声も鳴りを潜め、両岸の兵は天女のように舞い踊る娘にうっとり見とれ、喝采(かっさい)が沸き起こった。ところが、舞い終わった2人は「敵の前に生き恥をさらした」と抱き合い淵(ふち)に身を投じたという。
また、稚児石についても伝説がある。木幡山で戦勝を得た源義家が正法壇の法印に凱旋(がいせん)の迎えを受けた際、義家は岩上で舞う童児の姿を間近に見ようと川を渡ったところ、馬もろともに落下してしまった。馬は死んだが、義家はけがひとつなかった。落馬跡とその血痕が石に残り「血駒石」と言われたが、いつか「稚児石」と呼称されるようになったという。
|
| >>>
MAP |
|
|
稚児舞台の悲話 「東和の昔ばなし」(斎藤一郎兵衛著)に記されている。話を聞いた姥(うば)は悲しみのあまり、娘たちが消えた淵に身を投げ後を追ったとされる。
▽問い合わせ=二本松市安達支所(電話0243・23・9024)へ。 |
|
【 23 】
2008年9月4日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
( 文・安田茂 写真・一ノ瀬澄雄 )
|