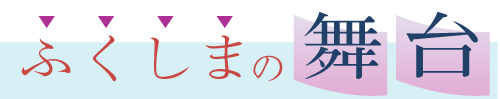 |
|
立子山の天正寺
(福島市)
|
|
朝河貫一が育ったお寺
|
|

|
|
本堂の白壁に残る貫一の落書き。数頭の馬が筆で描かれている
|
山あいにたたずむ天正寺は、世界的な歴史学者朝河貫一(1873―1948)が幼少期を家族とともに過ごした場所だ。
1874(明治7)年、本堂脇の客殿に立子山小が開校。校長に貫一の父朝河正澄が採用され、一家は二本松から同寺に移り住んだ。貫一は12歳ごろまで立子山で育ったが、4歳までは同寺で暮らした。
福島市文化財保護指導員で同寺総代長の藤原孝雄さん(70)によると、立子山地区は明治になるまでの約200年間、幕府直轄地だったため、「農民から取れるものは何でも取る」という代官の施政の下、厳しい生活を強いられ、農民一揆が起きたほどだった。人々は明治政府になっても希望が持てず、荒れた生活を送っていたという。
そこに赴任したのが、旧二本松藩士の精神を受け継ぐ正澄だった。正澄は子どもだけでなく村の若者や女性の教育にも力を注ぎ、今でいう勉強会や教養講座のような場をつくり、風紀と知識の向上に努めた。わが子の教育にも熱心で、貫一が5歳のころには「日本外史」や「四書五経」など儒教の精神を教えた。
同寺本堂の白壁には貫一が4歳のときに書いたとされる落書きが残る。どこかコミカルな馬の群れ。貫一が立子山の風土から何を吸収し、成長したのか。静まりかえった境内で思いをめぐらす。
日露戦争から太平洋戦争に至るまで世界協調を訴えていた貫一。藤原さんは「今なお世界で戦火は絶えない。その理念を伝えていきたい」と話している。
|
| >>>
MAP |
|
|
曹洞宗太平山天正寺 約500年前に建立された禅寺。1874年から1876年まで立子山小として使用された。貫一の祖母ヤソと母エヒの墓がある。住所は福島市立子山字寺窪2。
▽問い合わせ=天正寺総代長藤原孝雄さん(電話024・597・2022) |
|
【 38 】
2009年1月8日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
(
文・佐藤綾 写真・矢内靖史 )
|