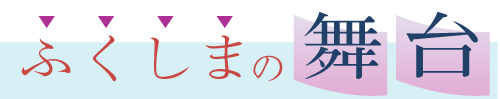 |
|
大尽屋敷跡
(葛尾村)
|
|
莫大な富、敷地2ヘクタールに蔵48棟
|
|

|
|
高さ10メートルほどの巨石に刻まれた磨崖仏(まがいぶつ)
|
阿武隈山系の中央部、山懐に抱かれた葛尾村の古い街道沿いに残る大尽屋敷跡。江戸時代から明治時代にかけ、栄華を誇った豪商松本三九郎一族の夢の跡だ。
蔵が48棟あったといわれる広さ2ヘクタール余りの敷地には、近江八景を模した池、能狂言の舞台跡などがあり、当時の豪華な暮らしぶりを今に伝える。
松本氏の祖は、左大臣藤原魚名の末裔(まつえい)で信州葛尾城主の一族だったが、領地を追われて移り住んだといわれ、「葛尾」の地名は故郷をしのび名付けられたという。
松本氏は、製鉄業、養蚕生糸商、酒造業、産馬などで莫大(ばくだい)な富を築き上げ、いつしか「葛尾大尽」と呼ばれるようになった。一族の繁栄は、松本三九郎を初めて名乗った6代目から11代目まで約200年間続いた。最盛期の江戸中期には、近隣の三春藩、相馬藩、棚倉藩に大金を献上し商売の独占権を手に入れた。商圏は、江戸をはじめ京阪地域にまで及び、最盛期には100人を超える使用人を抱えていたという。
村には、一族の豪勢を物語るエピソードが伝わる。三春城主が屋敷を訪れた際、屋敷向かいの山に火を付け、山が燃え上がる様子を風流として楽しんだという。
時は移り、明治の世となると家業の製鉄業が衰退。1871(明治4)年と1933(昭和8)年には、火災が起き屋敷のほとんどを焼失した。
現在も残る築城石の石垣が、栄枯盛衰の無常を物語っている。
|
| >>>
MAP |
|
|
大尽屋敷跡 かつらお大尽屋敷跡公園として整備。製鉄の歴史を知る上での貴重な歴史的遺産。裏山には松本一族の先祖供養のための磨崖仏(まがいぶつ)が往時を伝える。
▽問い合わせ=葛尾村公民館(電話0240・29・2008) |
|
【 41 】
2009年1月29日 福島民友新聞社・木曜ナビ
ほっと面掲載
|
|
(
文・木口拓哉 写真・吉田義広 )
|