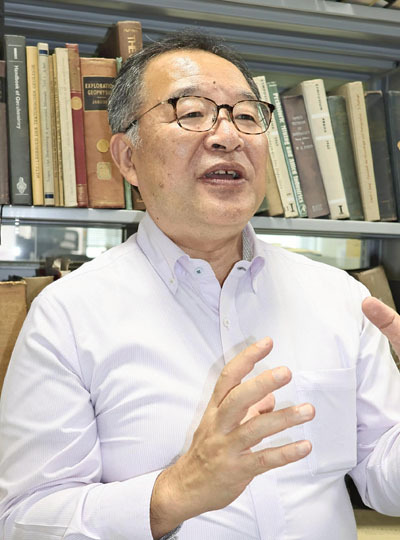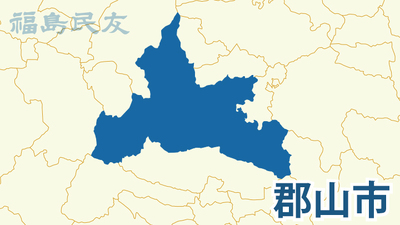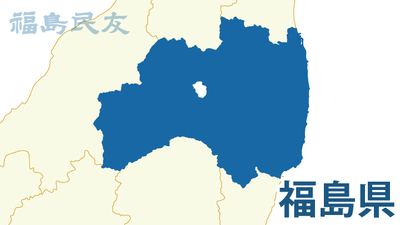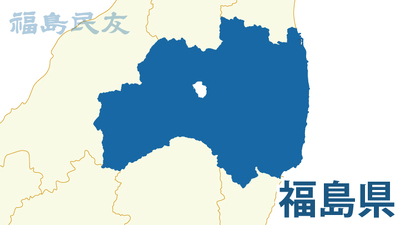東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から11年6カ月。本県復興の大前提となる第1原発の廃炉では溶け落ちた核燃料(デブリ)や処理水の扱いを巡り、工程ごとに一進一退の状況が続く。 東京電力福島第1原発で増え続ける処理水を巡り、東電が海洋放出に使う海底トンネルの掘削など放出設備の工事に着手した。政府と東電は来春をめどに海洋放出を始める方針を崩していないが、8月から本格的に始まった工事は遅れており、...
この記事は会員専用記事です
残り1,131文字(全文1,331文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。