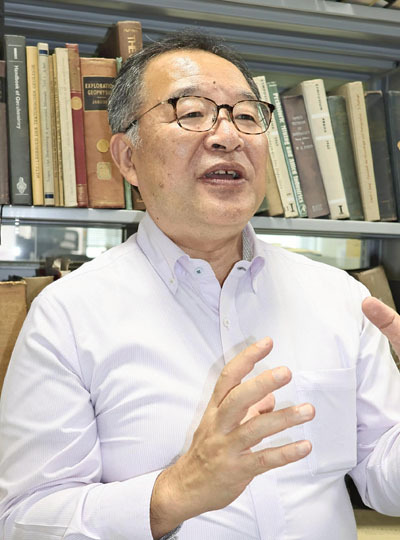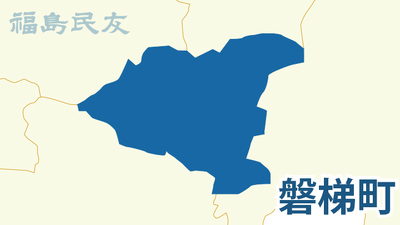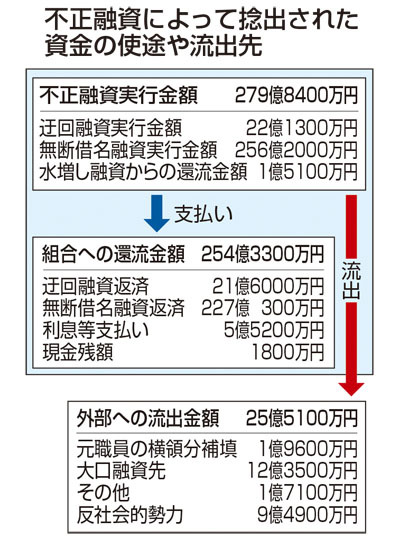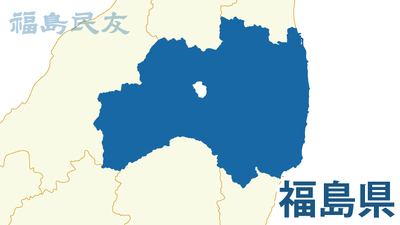東京電力福島第1原発事故から10年が経過した。廃炉の状況について原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)の山名元理事長に聞いた。 第1原発を浜通りにとってリスクのない状態にする ―廃炉の達成状況をどのように評価するか。 「遠くの方に見えている山の頂上に向かって、道なき道を暗中模索してきたようなものだ。原発事故直後は原子炉の様子など何も分からなかった。10年かけてリスクの高いところが分かり、工学...
この記事は会員専用記事です
残り3,659文字(全文3,859文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。