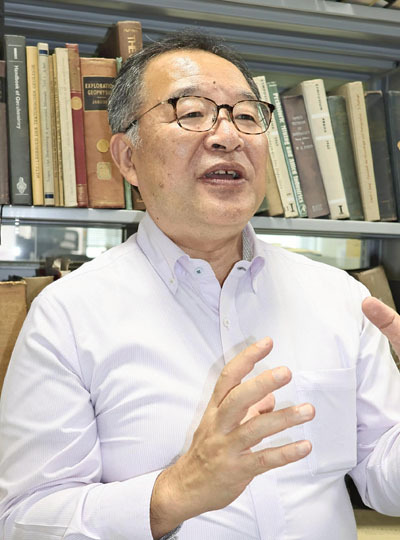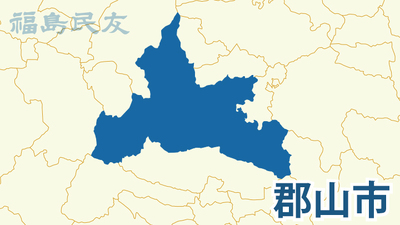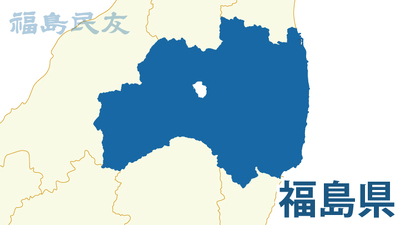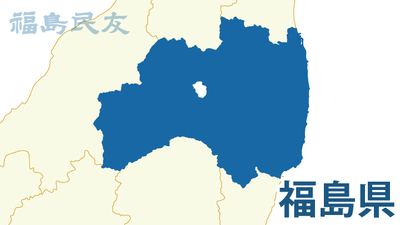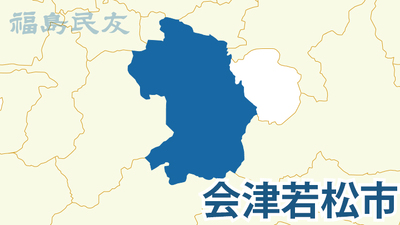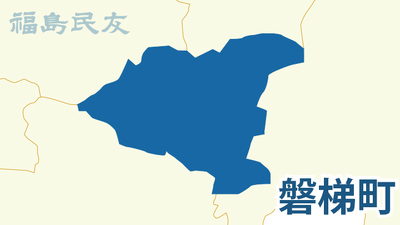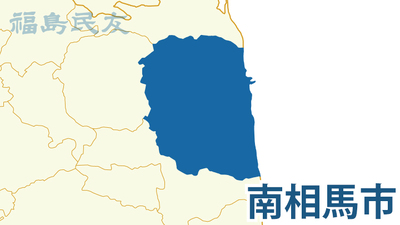「あら、元気だった。事務所の近くに来たらまわってよ」。南相馬市社会福祉協議会(社協)の職員が、朝のラジオ体操に集まってきた高齢者らに声を掛けた。会場は同市原町区にある復興公営住宅の「南町団地」。団地には、東京電力福島第1原発事故により同市小高区や浪江町から避難してきた住民が暮らしている。ラジオ体操は入居者同士の交流の場として行われていた。 細かい気付き不可欠 体を動かした参加者が部屋に戻っていく...
この記事は会員専用記事です
残り3,730文字(全文3,930文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。