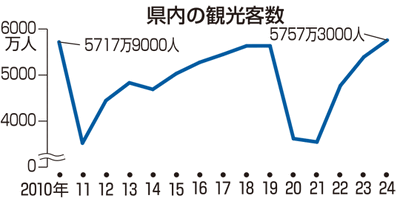全国の視聴者に勇気を与え続けた朝ドラ「エール」。平均視聴率は関東地区が20.1%と大台を超え、本県は32.1%と驚きの高視聴率だった。11月下旬に感動のフィナーレを迎えた今、物語のモデルとなった古関裕而と妻金子(きんこ)の長男・正裕さん(74)に「エール」の感想や古関メロディーへの思いなどについて聞いた。 感動的なクライマックスだったが、本編最終回の感想は。 「音(二階堂ふみさん)の弱々しい足...
この記事は会員専用記事です
残り2,445文字(全文2,645文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。