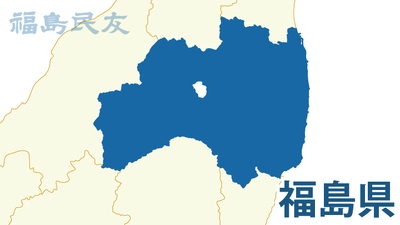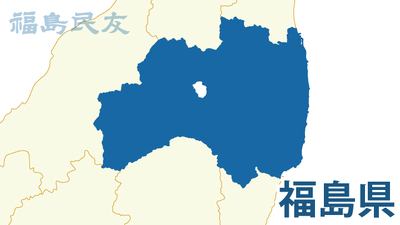3月から日曜日に連載してきた「エールのB面」も今回で最終回。フィナーレを飾るのはコメディアンの萩本欽一さん(79)。芸能人や有名人とその家族が歌を競い合う「オールスター家族対抗歌合戦」(フジテレビ系)で司会を務め、審査員長だった古関裕而と約12年にわたって共演、お茶の間の人気を集めた。今も「古関先生」と慕い、「エール」を特別な思いで視聴した"欽ちゃん"が番組での共演の思い出や知られざる秘話を語った...
この記事は会員専用記事です
残り2,454文字(全文2,654文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。