おくのほそ道まわり道
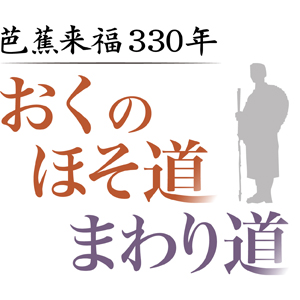
古今東西、旅に対する人々の憧れは尽きない。先人は旅路の感慨を詩や散文に記し、その作品がさらに人々を旅へと誘う。そんな紀行文学の中でも、根強い人気を誇るのが江戸時代初期の俳人松尾芭蕉(1644~94年)の「おくのほそ道」だ。2019年は、芭蕉が本県を含む東北、北陸を巡った「おくのほそ道」の旅から330年。膨大な旅の情報があふれる現代にも、人々を引き付ける芭蕉の旅の魅力とは何だろう。福島民友新聞は、そんな問いへの答えを探しに、芭蕉の足跡をたどる旅に出る。
【旅の終わりに】俳人・長谷川櫂さん(下) かるみの先に心の安寧
04/27 14:01
松尾芭蕉来福330年の節目に始まった連載「おくのほそ道まわり道」は、今回で幕を閉じる。最後に、芭蕉は、この奥州・北陸の旅でつかんだ人生観を、どのように作品に昇華させたのか、俳人の長谷川…







































