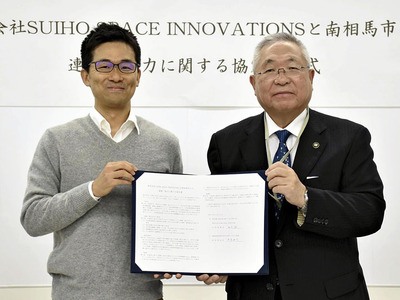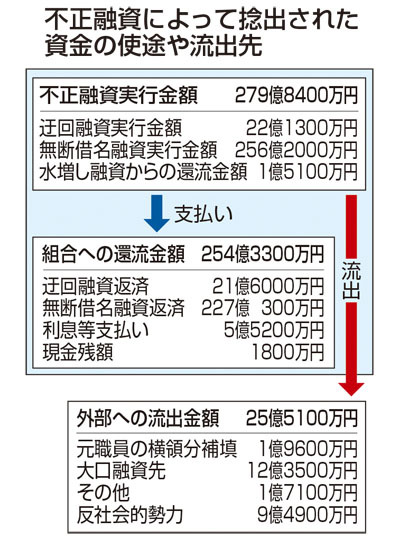台湾が東京電力福島第1原発事故後に導入した輸入規制に関し、日本産の全食品に求めている産地証明書や、本県など5県の食品に求めている放射性物質の検査報告書の提出義務を廃止する方針を決めた。実現すれば、事故後に導入した規制の全面撤廃となる。60日間の意見公募を実施し、問題がなければ最終決定する。
本県などからの食品輸入を巡り、台湾は2016年に当時の政権が規制緩和の方針を示したが、18年の住民投票で禁輸継続が決定した。22年に報告書などの提出を義務づけた上で禁輸を解除し、24年からはキノコ類なども輸出できるようになっていた。
台湾は本県産の食品を含め、事故後の輸入食品の検査で全て問題がなかったため、世界の多くの国の管理方法に合わせるとしている。事故前と同様の形での輸出が可能となる。東アジアで初めて、規制を完全撤廃する方針を示した意義は大きい。
原発事故や同原発の処理水放出を理由として輸入規制が続いているのはロシア、中国、香港、マカオ、韓国で、ロシアを除けば東アジアの国と地域が占めている。台湾との貿易実績を着実に積み上げ、関係改善の進む韓国をはじめ、ほかの国と地域の規制撤廃に生かしていくことが重要だ。
台湾は事故前まで、モモの輸出量の9割を占めるなど、本県にとって食品輸出の主要な相手先だった。最新の日本酒の輸出実績では、米国に次いで2番目に多く、本県産食品をさらに受け入れる素地は十分にあるとみられる。県などは規制撤廃を見据え、販路の再開拓やPR強化など、輸出量回復に向けた取り組みを急ぐべきだ。
報告書が不要となり、輸出業者の負担が軽減される一方で、課題となりそうなのは厳しい検疫への対応だ。モモの輸出は23年度に50キロで24年度は実績なし、コメは24年度の200キロにとどまっているのも、それが大きな理由だ。
モモの生産量が多いJAふくしま未来の担当者は「条件を満たさないものがあれば、輸入を止められてしまう。本県だけではなく、ほかの産地にも迷惑がかかる」と話す。県やJAには、検疫への対応を生産者に周知するなどして、輸出する食品の品質管理を徹底する必要がある。
福島空港と台湾を結ぶ定期チャーター便の運航などを背景に、本県の外国人宿泊客のうち半数超を台湾からの来訪者が占めている。食品輸出の促進と観光を通じた人の行き来が、相互に好影響をもたらすことを期待したい。