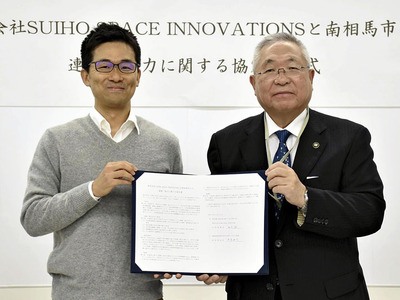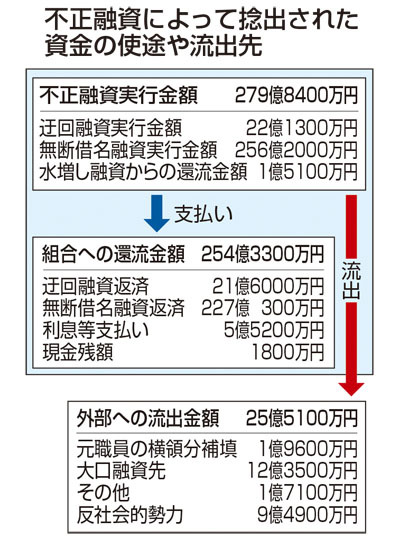老いは、人以外にはほとんど見られない特徴なのだという。東京大定量生命科学研究所の小林武彦教授は、年齢を重ねるなどしたシニア層のいる集団は、そうでない集団よりもさまざまな点で有利だったから―と、生物学の視点からとその理由を指摘する。
小林氏は、シニア層には多くの技術や知識が蓄積されており、それが引き継がれていくことで、より安定した豊かな社会がつくられてきたと説明する。また年齢を重ねたことで私欲が少なくなる傾向があるため、全体の利益を中心に判断できるとのメリットもあるという(「なぜヒトだけが老いるのか」講談社)。
あすは敬老の日だ。高齢者がそれぞれの培った技術や知恵を発揮し、社会に関わっていくことは、続く世代が豊かな社会を受け継いでいく土台となる。
高齢者が社会との接点を保ち続けることは、心身の衰えを防ぐ上で極めて意義のあることだ。健康を守るとの利点も踏まえつつ、高齢者には積極的に、これまでの経験や、年を重ねたからこそ分かる視点を若い世代へと伝えていってもらいたい。
政府が昨年まとめた高齢社会対策大綱は65歳以上の就業者が増加傾向にあることを背景に、「年齢によって『支える側』と『支えられる側』を画することは実態に合わない」との見解を示した。その上で、若年世代から高齢世代までの全ての人が希望に応じて、「支える側」にも「支えられる側」にもなれる経済社会の構築を目指す―としている。
大綱が指摘するように、高齢者の就業率は年々伸びている。しかし、同じ仕事をしていても、待遇は定年前よりも低くなるのが一般的だ。これでは意欲を維持するのが難しいとの指摘がある。
県内の65歳以上の高齢者は約58万人で、全人口の3分の1を超えている。そのなかで健康を保ち、働く意欲を持っている人には、「支える側」として存分に活躍できる場が与えられてしかるべきだ。どうやって高齢者に力を発揮してもらえるようにするかを全世代で考える必要がある。
人口減少などにより人手不足が恒常化している現状を踏まえれば、優秀な高齢者を確保できるかどうかは、企業などの集団の成長を左右する重要な要素だろう。法律による義務付けや、安く雇えるといった費用負担面のメリットにとどまらず、高齢者が働き手として適正な評価と待遇を得られるような仕組みを構築していかなければならない。