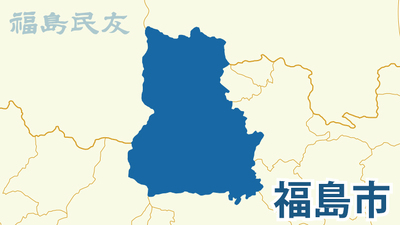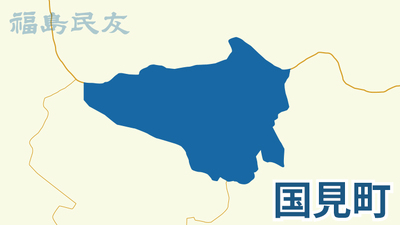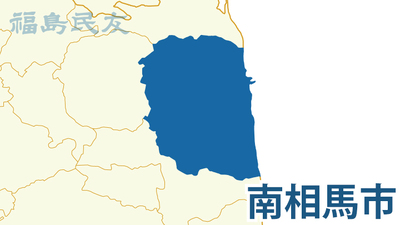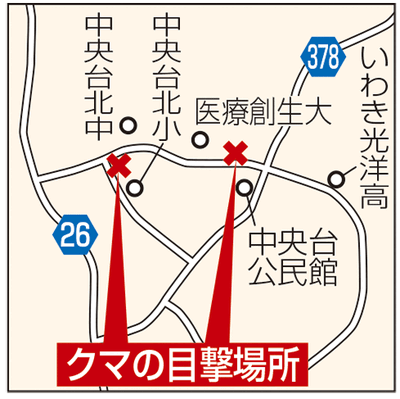変容する社会に期待される役割とは
パルシステム連合会は10月9日(木)、東京都新宿区の本部で学習会「国際協同組合年にあたり日本の協同組合と生活の状況・課題」を開催しました。社会学者の近本聡子さんを講師に招き、世界で期待が高まっている協同組合の役割について考えました。
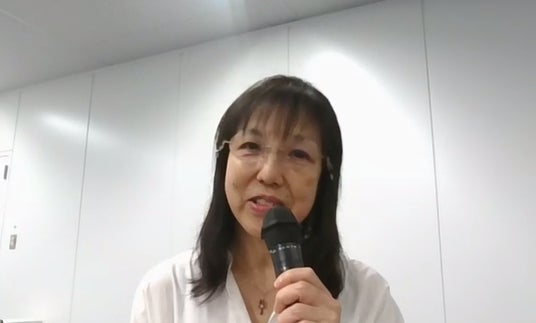
講演する近本さん
協同組合に期待される「包摂」
学習会は、会場とオンラインで開催され、利用者や役職員94人が参加しました。社会学者で元愛知学泉大学教授を務めた近本さんから、国際協同組合年が決議された背景や協同組合の歴史、日本の生協が抱える課題と期待などが述べられました。
冒頭、近本さんは「協同組合はビジネスツールです」と言い切りました。紛争や格差拡大、気候変動による災害などが世界中で発生するなか「困っている人、排除される人が増えています。協同組合という組織のしくみを用いてこうした人々を取り込み、経済的、社会的な発展を促進しようという意図が込められています」と決議に至った背景を説明し、キーワードに「包摂」を挙げました。
日本の協同組合は、農協や生協などの活動分野ごとに根拠となる法律や所轄官庁が別に定められ、制度が異なります。そのなかで生協は戦後、理容や保育などさまざまな業態で誕生し、小売業態が大規模化しました。
近本さんは「包摂」の視点から「できたこと」「できなかったこと」の整理を提起しました。「利用者、事業高とも成長し『包摂は拡大している』といえるでしょう。一方で、経済的に見合わず利用をあきらめた人や、生協の影響で事業継続を断念する人がいることも事実です」と指摘。集団行動には必ず排除が生まれてしまう現実をあらためて示しました。
縮小する社会にともなう「文化変容」
利用者の多数を占める女性の活躍については「地域活動から女性が撤退し縮小しており、どの生協でも大きな課題になっています。家族へ還元されていた女性の社会的なつながりは、仕事する人が増えたことで社会に声が届きにくくなっています」と説明しました。そのうえで「生協は、社会的に女性が活躍する姿を具体的に提示できていないのでは」と投げかけました。
日本は将来、少子化がさらに進むことが予想されています。社会そのものの縮小に対応するためには、多様な人がそれぞれの個性を発揮し、それを認める社会へ成熟する必要があります。ただし実現には、これまでと異なる価値観や生活様式を受け入れなければなりません。多様性を受け入れるツールのひとつとして近本さんは、地域の人が集まる生協の共同購入やそれ以外の新たなグループ購入に期待しました。
最後に近本さんは「多様性を包摂することで生まれる文化の変容に、日本社会が耐えられるか」が課題とし、参加者へ「知ること」「認めること」を勧めます。「これまでの活動に誇りを持ちながら、さらに『どうすべきか』を問いかけてください」と呼びかけました。
パルシステムグループはこれからも、協同組合の力によるよりよい社会づくりを推進します。
 パルシステム生活協同組合連合会
パルシステム生活協同組合連合会所在地:東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長:渋澤温之
13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人(2025年3月末現在)
会員生協:パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ
HP:https://www.pal-system.co.jp/

2025年は国際協同組合年です
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ