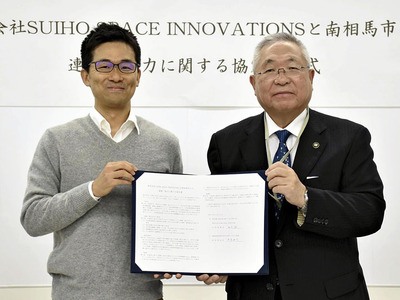約4億円の公金を損失させただけでなく、企業版ふるさと納税による寄付の受け皿が当面失われることとなった。不適切な行政手続きで、町民の不利益が拡大する事態を招いた町の責任は重い。
内閣府は、企業版ふるさと納税で不適切な運用があったとして、寄付を受けるために国見町が策定した地域再生計画の認定を取り消した。官民連携で開発した高規格救急車を貸し出す事業を巡り、寄付の代償として、町が寄付会社に便宜を図ったと判断された。取り消しは全国で初めてだ。
内閣府は取り消しの文書で、事業を町に提案した宮城県の企業が受注した場合には、寄付企業の子会社に救急車が発注される可能性が高いことを、町職員らが認識していたと指摘した。その上で、事実上、宮城県の企業しか受注できないような条件を設けるなど「殊更有利に取り扱った」とした。
町議会の調査特別委員会(百条委員会)の調査では、職員と企業による複数回にわたる会食や内部文書のやりとりなど、不適切な関係が明らかになった。再び地域再生計画を策定したとしても、企業と同化するような組織のままでは同じ轍(てつ)を踏むことになると、町は肝に銘じるべきだ。
企業版ふるさと納税は寄付額の最大9割の税控除を受けられ、節税対策に利用される面がある。町の便宜供与により、企業側は税優遇に加え、救急車の販売益などを得た形となり、資金還流の疑いの目が向けられている。
救急車事業には、特殊な車両の仕様書作成の経緯や、研究開発したとされる救急車が短期間で納車された点など、不自然な部分が多く残っている。百条委の調査では、関係する職員らが記録を廃棄したので分からない、記憶にないなどの弁明を繰り返しており、隠蔽(いんぺい)の疑いも晴れていない。
失墜した町政への信頼を回復するためには、組織のうみを出し切ることが欠かせない。新しい町長の下、町は主体的に調査し、実態をつまびらかにすべきだ。
国見町の問題を受け、伊東良孝地方創生担当相は、企業版ふるさと納税制度を改善する考えを示した。本年度で期限が切れる同制度を延長するためには、不備を正す必要があると判断したのだろう。
寄付企業の子会社による事業受注や、匿名での寄付を可能とする同制度は、かねて悪用される恐れがあると指摘されていた。国の対応は遅きに失したと言わざるを得ない。受注要件の厳格化や寄付の透明性を確保するなど、健全な制度へと改める必要がある。