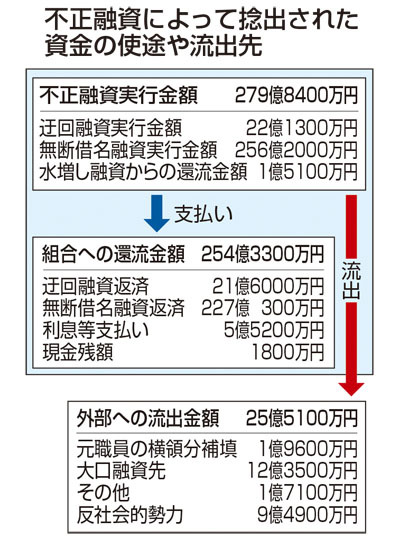プラスチックごみによる環境汚染が世界で広がっている。各国は立場の違いを乗り越え、汚染に歯止めをかけることが急務だ。
プラごみによる汚染を防ぐための初の国際条約作りで、政府間交渉委員会は条約案への合意を見送った。生産規制を巡る意見の隔たりがあり、国連環境総会で決めた年内の合意に至らなかった。
国連などによると、年間約1千万トンのプラごみが海に流れ出ている。人体や生態系に有害な添加物の入った製品などが、マイクロプラスチックと呼ばれる微粒子となって体内に取り込まれることによる健康被害が懸念されている。
プラスチックの生産や焼却時には温室効果ガスが排出される。2019年に世界で8億5千万トンだったプラスチック由来の二酸化炭素(CO2)排出量は、生産量の増大に伴い、30年には日本全体のCO2排出量に匹敵する13億4千万トンに増えるとの予測がある。
プラスチックによる汚染はオゾンホールの問題と並ぶ地球規模の課題だ。早期に会合を再開し、条約を策定する必要がある。
生産規制を巡っては、欧州連合(EU)や、プラごみの漂着と温暖化による海面上昇の危機に直面する島しょ国などが、生産量の削減目標を含めた厳しい規制を求めている。一方、プラスチックの原料となる石油を産出する中東諸国などは規制に反対している。
会合では生産規制抜きで条約を策定した後、第1回締約国会議で規制目標を改めて採択する妥協案が提案されたが、産油国は反対した。1人当たりのプラごみ排出量が世界2位の日本は、一律でなく各国の状況に応じた規制にするべきとの消極的な立場で、提案には名を連ねなかった。
プラ製品を大量生産、大量消費する経済活動により、島しょ国の生活や日本を含む将来世代の健康が脅かされている。自国の利益を守るために妥協案すら反対する産油国や、玉虫色の姿勢を取る日本は無責任と言わざるを得ない。
産油国などに譲歩していては、実行性の乏しい条約になりかねない。策定時からの生産規制が不可欠で、日本はEUや島しょ国と足並みをそろえるべきだ。
日本で排出されるプラごみの約7割は、発電や熱回収されるものを含めて焼却されている。リサイクルが不十分な現状を踏まえ、企業には過剰包装を見直し、消費者にはできる限り使い捨てを減らすことなどが求められる。
条約の策定に向けた議論を、国内のプラ製品への依存度を下げる契機とすることが重要だ。