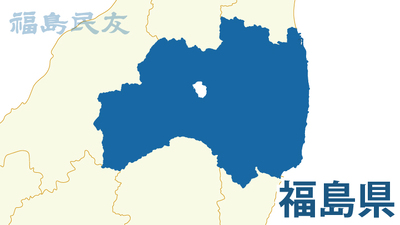かつては起伏に富んだ地区だったという。大量の土砂はいくつもの谷を埋め、住宅など約3千棟あった建物は半数余りが姿を消した。人々の営みを想像することが、今はもう難しい。
2月18日、東京電力福島第1原発を囲むように整備された中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)を訪ねた。
敷地面積は福島空港九つ分に匹敵する1600ヘクタール。原発事故後、県内各地の除染で出た土壌と廃棄物の計1407万立方メートルが運び込まれた。
搬入作業は峠を越え、1日3千台を超えて往来したダンプは20分の1ほどに減った。稼働中の処理施設もなくなりつつある。
搬入開始から10年。広大な土地に静けさが漂う。
「断固反対。先祖伝来の地を奪わないでほしい」
「施設は必要だが、古里を捨てたくない」
「そのまま最終処分場になるのではないか」
原発事故から間もない頃、中間貯蔵施設の候補地となった大熊、双葉両町の住民は揺れていた。大量に出る除染土壌の置き場所は喫緊の課題。誰かが犠牲にならなければ復興は進まない。しかし、受け入れることは帰る場所の喪失を意味する。長引く避難生活に加え、重い葛藤が心をすり減らした。
交渉は3年を要した。県と2町は中間貯蔵開始から30年以内の県外最終処分を条件に、建設を容認した。
「私たちは故郷を失い、立ち入りすらできなくなる。それでも、復興が前に進んでほしい」。行政区長の一人は当時の無念を明かす。
県内に1372カ所あった仮置き場の99%は中間貯蔵施設への輸送を終えた。除染が一定の前進を果たした一方、中間貯蔵の「先」は見えない。
最終処分量を減らす政府の再生利用方針に対し、県外では「放射能汚染土を持ち込むな」などと反対運動が続いている。
必要性は認めるが、私の家の裏庭ではごめんだ。
こうした人間心理は、英単語の頭文字を取り「NIMBY(ニンビー=Not In My BackYard)」と呼ばれる。ごみ処理場や火葬場と同様、復興の陰で大量生産された除染土壌も「迷惑施設」になって久しい。
NIMBY問題に詳しい福島大元副学長の清水修二名誉教授は「原子力の問題はどれだけ国民が人ごとにせず、わがこととして考えられるかに懸かっている」と指摘。「第1原発は首都圏に電力を供給し、日本の経済発展を支えた。決して福島だけの問題ではない」と語った。
県外最終処分の約束は、原発事故後に県民が受けた長期避難や中間貯蔵などの負担を広く分かち合う理念が根底にある。議論に一石を投じる動きも、少しずつだが出始めた。
清水氏は言う。「仮に人口の少ないへき地で受け入れたとしても、根本的な解決にはならない。みんなが当事者意識を持ち、話し合うことが大切だ」
約束の期限まで、12日で残り20年となった。
◇
ご意見、ご感想、情報をお寄せください。
◆〒960ー8648(住所不要)福島民友新聞社編集局「約束の行方」係
◆ファクス 024・523・1657
◆メール yakusoku@minyu.jp