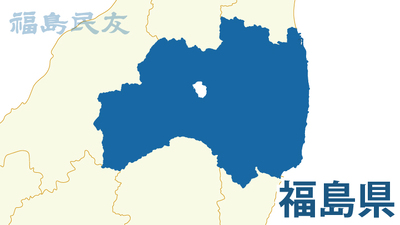政府が約束した除染土壌などの県外最終処分期限まであと20年。第1部は、関係者の証言などから残された時間の意味を問う。
◇
「残された時間はあと20年しかない。環境省は当初の約束を誠実に果たしてほしい」
昨年12月、中間貯蔵施設地権者会長の門馬好春さん(67)が迫った。環境省が大熊町で開いた地権者向け説明会での一幕だ。
門馬さんは冒頭、約束の実現に向け、早期の対応を求める要望書を浅尾慶一郎環境相宛てに提出した。文面には今まで何度も伝えてきた言葉が並んでいた。
約束とは、東京電力福島第1原発事故後に県内の除染で出た土壌と廃棄物を2045年3月12日までに、県外で最終処分することを指す。
15年3月13日、中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)に土壌などの搬入が始まった。中間貯蔵・環境安全事業株式会社法は、この日から30年以内の県外処分を定めている。
あれから10年が経過した。
環境省は戦略目標に位置付けた本年度、頻繁に学識経験者らと会合を開き、動きを活発化させている。
除染土壌の総量は今後の発生見込みを含め、1485万立方メートル。これに草木など廃棄物の焼却灰42万トンも加わる。各辺1メートルの大型土のう袋に詰めて福島市から真っすぐ並べた場合、南アフリカまで届く。
この膨大な量をいかに減らし、最終処分を実現するか。政府は早くから〈1〉低濃度土壌の再生利用〈2〉減容化(濃縮)―の二つに照準を定め、戦略を練ってきた。
しかし、土壌の大部分を当て込む再生利用は県内でも、県外でも進まない。小規模実証事業さえ安全性が疑問視され、計画を持ち込むたびに地域から猛反発を受けてきた。
もう一方の減容化も関係者の頭を悩ませる。
「減容化の事前準備や全量搬出後の片付けに3年ずつかかるとして残りは(実質)14年。既に『ぎりぎり』のタイミングに来ている」
国立環境研究所福島地域協働研究拠点の遠藤和人廃棄物・資源循環研究室長が明かす。対応できる国内企業も少なく「時間が経過すればするほど、技術的に取れる選択肢は狭まっていく」と指摘した。
こうした現実とは裏腹に、今年2月に公表された同省の工程表で、25年度以降の時間軸はほぼ白紙だった。
門馬さんは「帰りたくても帰れないまま、痛ましい話も聞こえてくる。悔しくてたまらず、この10年間で県外のどこに持っていくか決めてほしかった」と語気を強める。地権者2360人の多くは高齢で、既に亡くなった親戚や同級生も少なくない。
「廃炉と中間貯蔵事業が終了して初めて本当の意味の復興をスタートできる。将来世代のために、私たちはバトンを渡す責任がある」と門馬さんが言う。「この約束は絶対に守られなければならない。今は3分の1の通過点であり、政府には早く道筋を付けるよう求め続ける」
刻々と近づく期限を前に、焦燥だけが募る。