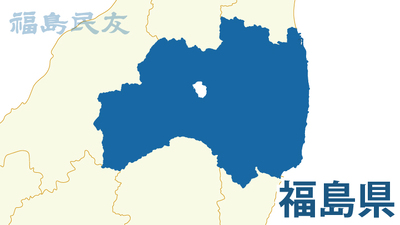未来の命を守りたい―。東日本大震災と原子力災害の記憶を伝える、語り部の仲間づくりに向けた事業が浪江町で5月にスタートする。講師を務めるのは「浪江まち物語つたえ隊」として紙芝居を使って語り部をしている同町の八島妃彩(ひさい)さん(59)と岡洋子さん(64)の2人。「伝えて助かる命があるならば、ずっとずっと続くようにつなげていきたい」と未来への種をまく。
「見えない恐怖、分からないことへの不安はいつまでも人の心を傷つけるのです。それが原発事故です」。今月上旬、岡さんが自宅を改装したカフェで、首都圏からの来訪者に紙芝居を披露した。涙を拭う人もいれば、言葉を失う人も。「また聞きに来ます」。そう言って帰っていく人もいた。
50作品以上
「つたえ隊」は、紙芝居でふるさとの記憶や思い出を語り継いでいこうと、2014年6月に町民有志で発足した。紙芝居は、同町の語り部佐々木ヤス子さん(12年6月死去)が披露していた昔話と、震災時の実話が題材となっており、浪江にまつわる物語は50作品以上となっている。
一方で現在、語り部として活動しているのは八島さんと岡さんを含めて4人だけ。活動は年々先細る中で、語り部に関心を持ってもらおうと、町の公民館事業として後継者の育成に向けた取り組みが始まることになった。
昨年5月には「つたえ隊」で発足から会長を務め、語り部活動を支えてきた小沢是寛(よしひろ)さんが死去した。「震災は現在の物語かもしれないけど、将来的には昔話としてでも語り継いで残していく必要がある」。小沢さんが生前に語っていた思いも、講師を務める2人の背中を押した。
小沢さんから会長を引き継いだ八島さんは「体調を崩されてからも活動を気にかけてくれていた」と回顧。「小沢さんがいなかったらできなかった団体だからこそ、その遺志を紡いでいきたい」と決意する。
小沢さんに誘われて語り部を始めた岡さんは「小沢さんの浪江を思う気持ちは大きかった。それを私たちが受け継いで、若い人に引き継がなければいけない。つたえ隊と紙芝居はずっと残していくべきものだ」と力を込めた。