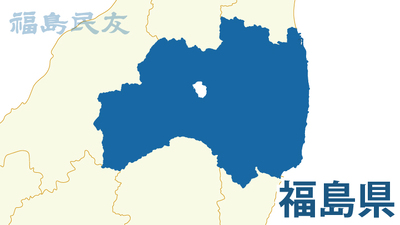東京電力福島第1原発事故から5カ月が過ぎた2011年8月27日。菅直人首相(当時)は県庁を訪ね、重い口を開いた。
「中間貯蔵施設は福島県にお願いせざるを得ない」
接見した佐藤雄平知事(同)の返事は「何の話ですか、突然」。根回しはなく、退陣あいさつだとばかり思っていた。寝耳に水の方針に対し、何度も「困惑している」と繰り返した。
この2カ月前、環境省は県に対し、最終処分場を県内に設けたい考えを水面下で伝えている。打診は一蹴(いっしゅう)され、代わりに示したのが「一時的な保管」をうたう中間貯蔵施設の構想だった。
国内の原発で重大事故など起きない―。そんな「安全神話」に染まり、政府は放射性物質が広範囲に飛散する事態を想定していなかった。当然、事故直後の対応の枠組みもない。
制度設計は急ピッチで進められた。11年8月には放射性物質汚染対処特別措置法が成立したが、この頃、県内各地で大量に発生する除染土壌が問題視されるようになった。
暫定的に確保した仮置き場の数は最終的に県内1372カ所に上る。「これがあり続ければ、いずれ観光や農業にも影響が及ぶ」。佐藤氏は中間貯蔵施設の必要性を認め、12年11月、地元に説明を尽くすことを条件に調査を受け入れた。
候補地は大熊、双葉両町に絞られ、「受け入れはやむを得ない」と考える地元住民は次第に増えた。復興を前に進めるための苦渋の選択だったが、なし崩しに「最終処分場」になる恐れを誰もが感じていた。
県と2町は譲れない一線を引き、政府が提示した「30年以内の県外最終処分」の法定化を迫った。佐藤氏は1月の取材に「法で定めなければ、時の内閣によって(国の)方針が変えられかねない。今、振り返っても当然の要望だった」と語った。政府は求めに応じ、30年間に及ぶ「約束」を法律に明記した。
「30年」の期間はどう導かれたのか。原発相、環境相の立場で調整を図った細野豪志衆院議員は「土壌の再生利用に必要な検討などを含めると、かなりの時間がかかると考えた。さまざまな調整の中で、30年という数字になった」と説明する。県民と交わした約束に、明確な根拠はなかった。
中間貯蔵開始から10年。当時、町職員として受け入れに関わった吉田淳大熊町長は「多くの人の苦悩があって実現した。そのことを決して忘れないでほしい」と強調。伊沢史朗双葉町長は「今でも受け入れが正しかったかどうか、自分の中で答えは出ていない」と明かした。
知事退任から10年がたった佐藤氏は「3年、5年、10年後を見据え、政府は行動計画を明確にすべきだ。約束は必ず守らなければいけない」と訴える。
根拠のない法定期限は地元、政府の双方にとって、重みを増し続けている。
写真=(右)