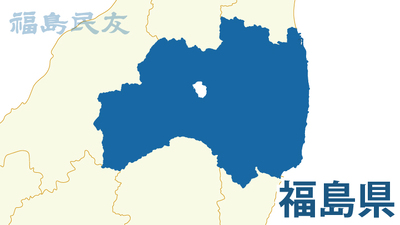国際原子力機関(IAEA)のグロッシ事務局長は2月19日、中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)に入った。IAEAトップの視察は初めて。東京電力福島第1原発事故後の除染で出た土壌と廃棄物の保管状況を確かめる狙いだ。
「報告を受けていた通り、非常に妥当なアプローチだと確認できた」。グロッシ氏は記者団の取材にこう語り、日本政府の計画を前向きに評価した。
この5カ月前、部下のアナ・クラーク廃棄物・環境安全課長が来日し、伊藤信太郎環境相(当時)に最終報告書を提出した。
IAEAは同省の求めで、県外最終処分方針の妥当性を調査。国際専門家ら10人のチームが現地視察などを経て、A4判86ページの冊子に見解をまとめた。
結論は端的だった。「環境省の取り組みは、IAEAの安全基準に合致している」。伊藤氏は「大変心強い。再生利用や最終処分に取り組む上で大きな支えになる」と頬を緩めた。
IAEAから「お墨付き」を得た流れは、23年8月に海洋放出が始まった第1原発の処理水と酷似する。処理水では、経済産業省がIAEAの調査結果を後ろ盾に、国内外に放出の安全性を訴えた。
対して違いもある。処理水に含まれる放射性物質トリチウムは世界中の原発から海に放出されているが、広範囲の除染で出た土壌を生活圏で再生利用した先例はない。除染土壌などの処分地は「県外」と規定され、1カ所に集めた現状からあえて運び出す必要もある。
こうした違いが壁となり、環境省が計画した県外3カ所での再生利用実証事業は「放射能を拡散すべきではない」などと地元の反発に遭い、事実上頓挫した。
処理水と除染土壌に詳しい関谷直也東京大教授は「海洋への影響懸念が国際的に問題となった処理水と違い、除染土壌は完全に国内の問題だ」と指摘。「海外で除染土壌の話は知られておらず、問題にもなっていない。(あくまで)国内の問題であり、IAEAの影響力は処理水の時と比べて小さいだろう」と語った。 グロッシ氏は「IAEAとして深く関与し続ける」と明言した。IAEAの幹部は「日本の試みは国際的に例がなく、他国にとって有益な参考事案になる」と本音を明かす。政府はこの狙いを逆手に取り、継続的に助言を受けることで、国内外に発信する安全性を補強したい考えだ。
他方、アナ氏は「最終処分に向けた時間軸は課題が非常に多い」と懸念を漏らしたこともある。
県外処分の期限まで残り20年。日本政府に「(合意形成を含む)社会的課題の解消には長い時間がかかる。信頼構築は決して急いではならない」と忠告する。