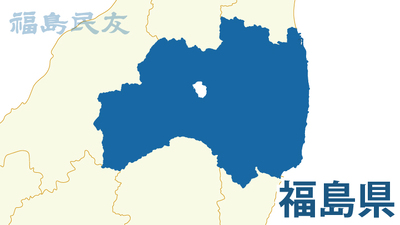栃木県日光市の鬼怒川沿いにある公園の外れ、利用者が立ち入ることの少ない一角に丘のように見える場所がある。
「盛り土の下に、フレコンバッグ270袋が入っています」。市職員は言った。
袋の中身は、東京電力福島第1原発事故後の除染で出た土壌計270トン。運び込まれて約10年、表面から草木が伸びきっていた。
原発事故は放射性物質を広範囲に飛散させた。国は福島以外で宮城や茨城など7県63市町村を「汚染状況重点調査地域」に指定し、ほぼ全ての自治体で除染が実施された。現在、53市町村がそれぞれ土壌を保管している。
保管場の数は7県で計2万8716カ所に上る。量は33万立方メートルと本県(1407万立方メートル)に比べて少ないが、民家や学校、公園などに広く分散している。9割の保管場では土壌を地下に埋めており、日常で目にしたり、話題になったりする機会はほとんどない。
地上で保管されたままの土壌も少なくはない。「長期間置いてあるのでそろそろ持っていってほしい」。同市の女性(74)は、自宅の裏手に残った三つの土のう袋を指さした。
原発事故から14年が経過し、保管場の近隣住民からは「このままそっとしておいてほしい」との声も聞こえてくる。一方、観光産業が主力の自治体などでは「早くどこかに持っていって」「風評被害が心配」などの意見も根強い。国に一日も早い対応を求める立場は、県内、県外とも同じだ。
環境省は近く、土壌の再生利用と最終処分の基準を策定する。県外でも同じく適用されるが、実施の責任主体は異なる。県内では同省が除染から最終処分まで一貫して担うのに対し、県外の場合、責任を負うのは各市町村だ。
県外の土壌の放射性物質濃度は99.9%が1キロ当たり8千ベクレル以下と低く、ほぼ全量が再生利用できる。とはいえ再生利用や最終処分は「正直、負担が重い」(日光市)のも実情。政府には「周辺住民の理解を得ることは難しい」「住民説明会に同席してほしい」などの反応が寄せられている。
初期の政府方針により、県外の除染土壌は各県内で埋め立て(最終)処分される。基準が策定されることを受け、日光市は新年度、埋め立て場所の検討や除染土壌を置く家庭から聞き取りする方向で準備に入った。
環境省の担当者は「各自治体に丸投げするつもりはない。技術面でサポートするほか、住民説明会にも同席し、しっかり伴走支援していく」と説明。早期の処分実現へ、地域と共に汗を流す考えを強調する。