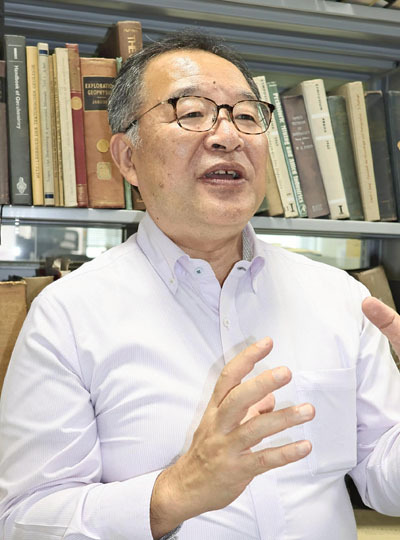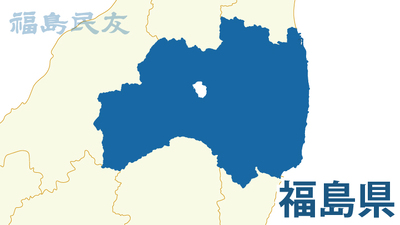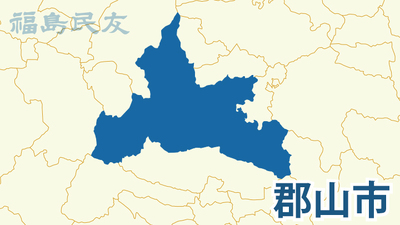東日本大震災と東京電力福島第1原発事故に伴う避難を経て、移住者も地域に加わる中、浜通りの被災地では自主防災の活動が重要な役割を担っている。全国的に災害が頻発し、地域の防災力強化が求められる中、住民たちは新たなコミュニティーを築きながら、災害から「共助」で命を守る体制づくりを進めている。 新たなコミュニティー 福島大との協力 【浪江町幾世橋地区】町内で最も居住人口が多い幾世橋地区(幾世橋、北幾世橋...
この記事は会員専用記事です
残り2,540文字(全文2,740文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。