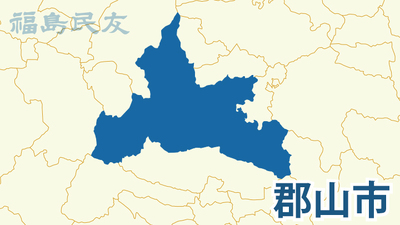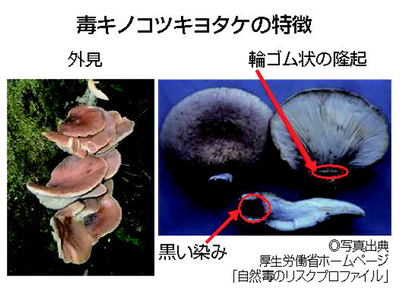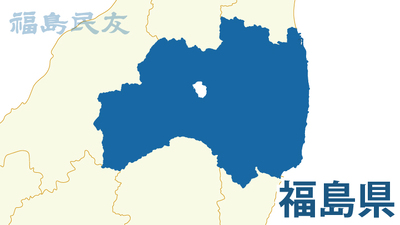東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出を巡り、福島大環境放射能研究所や東京大などの研究グループは2日、処理水に含まれる放射性物質トリチウムの挙動に関する研究結果を発表した。北太平洋の全域を25キロ四方ずつ区切って約70年後までシミュレーションした結果、第1原発から25キロ以遠では、放出開始前と比べ海水中のトリチウム濃度に増加がみられなかった。
研究グループは「トリチウムの長期的な分布に関し、客観的な科学的知見を提供できる可能性がある」としている。福島大によると、北太平洋全域にわたる規模でのシミュレーションは初めて。第1原発からより離れた海域の調査が目的のため、25キロ以内はシミュレーションしていない。
福島大からはマキシム・グシエフ特任准教授が参加した。研究グループは、海洋の特性や循環を数値的に表現する「全球海洋大循環モデル」を用いて、処理水放出が始まった2023年から99年までのトリチウム挙動をシミュレーションした。東電が公表している処理水の放出計画に基づき、地球温暖化の影響や海洋渦の動きも加味した。その結果、放出場所から25キロ以遠では、海水中のトリチウム濃度が検出限界値以下にとどまったという。
海域には原発事故後、本県産食品の輸入規制を続けている中国や香港、マカオなども含まれている。同大は研究成果を踏まえ「客観的な科学的知見を示し、輸入規制など風評被害の払拭につなげたい」としている。