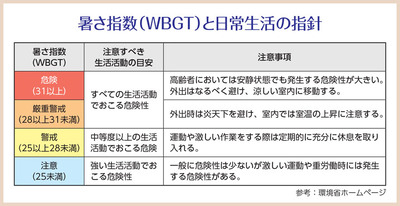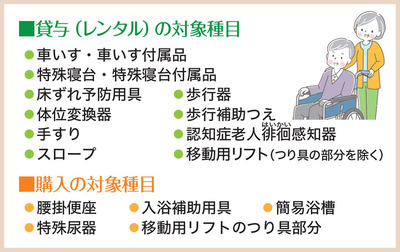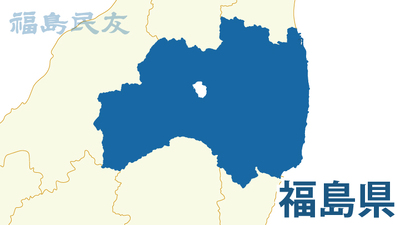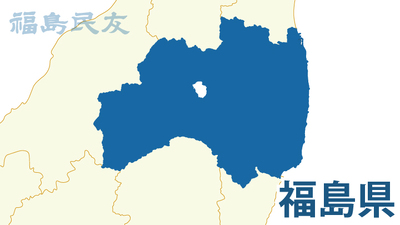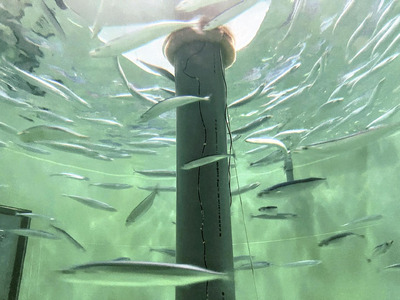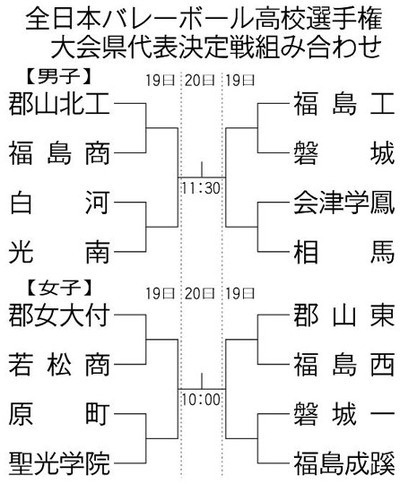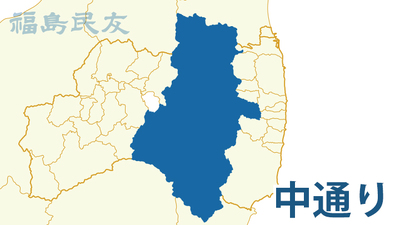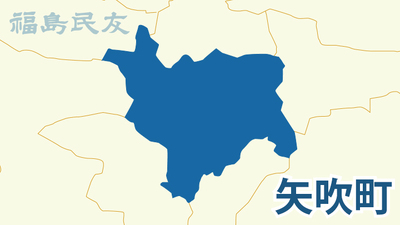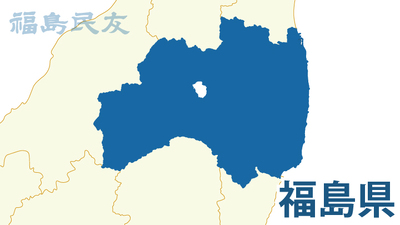今回は高齢者と小児の肥満について「肥満症診療ガイドライン2022」を参考にお話しします。 高齢者の肥満の特徴 肥満の基準になるBMI(体重㎏÷身長(m)÷身長(m))は年齢を重ねるに従い、増加傾向になります。なぜなら、加齢に伴い身長が低下するため、実際よりBMIが高値となることがあるからです。ウエスト周囲長も高齢になると増加傾向にあります。肥満を伴わないウエスト周囲長が高値である割合も加齢と共に...
この記事は会員専用記事です
残り1,703文字(全文1,903文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。