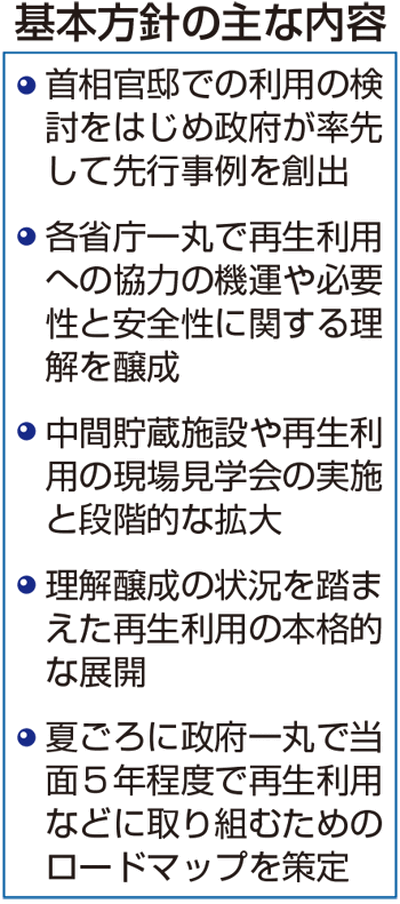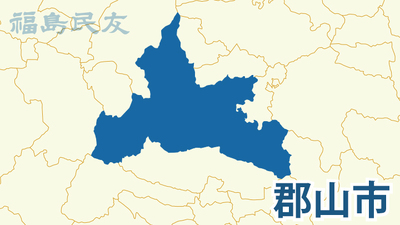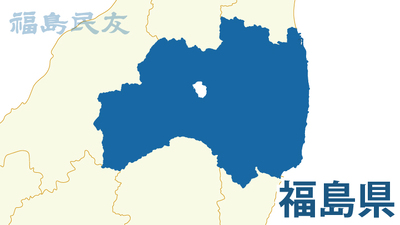政府は27日、東京電力福島第1原発事故後の除染で出た土壌の県外最終処分や再生利用の実現を目指す閣僚会議を開き、首相官邸での活用推進を盛り込んだ基本方針を決定した。花壇などを想定し、東京・霞が関の省庁敷地での利用も検討する。再生利用に対する国民の認知度は依然として低く、政府全体で必要性や安全性に関する情報を発信し、理解醸成に取り組む方針も明記した。
除染土壌を再生利用する取り組みは県内での実証事業以外で初となる。政府は先行事例をつくり、公共工事などで利用が拡大する状況を創出したい考えだが、受け入れに名乗りを上げる地域が現れるかどうかは不透明だ。
環境省によると、官邸や省庁敷地での具体的な使い方や土の量は現時点で決まっていないが、土地の造成を伴う一定程度の規模になる見通し。主に屋外での利用を見込んでいる。政府は利用現場周辺の空間放射線量をホームページなどで公開し、安全性の浸透につなげたい意向。
再生利用に関する情報発信を巡り、林芳正官房長官は閣僚会議で「国民の幅広い理解醸成が重要だ」と取り組みを強化するよう指示。今後、これまで情報発信の中心を担ってきた環境省と復興庁以外の各省庁も周知活動を本格化させる。環境省は「情報の発信源を増やすことで、少しでも多くの国民が情報に接する機会を創出する」としている。
基本方針を踏まえ、政府は夏ごろに再生利用と最終処分の実現に省庁全体で取り組むための工程表を取りまとめる。環境省は当初、工程表の期間を最終処分期限の2045年3月までとする方針だったが「政府内で調整した結果、まずは段階的に取り組む内容を示すべきだと判断した」として当面5年程度に改めた。
中間貯蔵施設(双葉町、大熊町)に運び込まれた除染土壌などは約1400万立方メートル(東京ドーム11杯分)で、最終処分の実現に向けては処分量を減らす再生利用の進展が鍵となる。環境省はこれまで東京都新宿区や埼玉県所沢市で再生利用の実証事業を計画したが、住民の反対で停滞している。