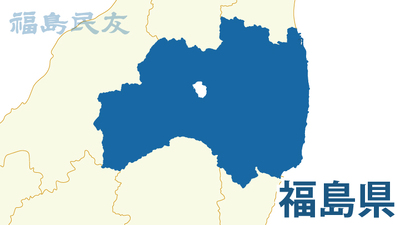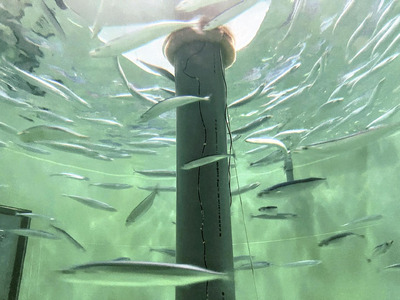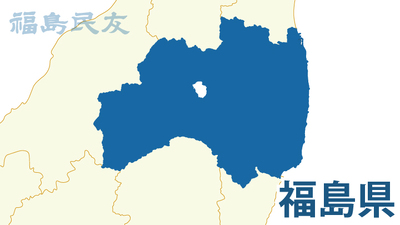恣意(しい)的で手続きを軽視した政策判断の危うさについて、警鐘を鳴らす判決だ。
国が2013~15年に生活保護費を引き下げたのは違法だとして、受給者が国と自治体に減額処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は引き下げを違法と認定し、処分を取り消した。国の賠償責任は否定した。同種訴訟は全国29都道府県で起こされ、地裁、高裁では判断が分かれていた。最高裁が統一判断を示したことで、今後同様の結論になるとみられる。
厚生労働省は3回に分け、生活保護のうち食費や光熱費など日常生活のための「生活扶助」の基準を段階的に引き下げ、計約670億円を削減した。最高裁はこのうち、物価変動に伴う減額分の約580億円について、物価の変動率のみでは消費実態を把握するのに十分と言えず、専門家らの検討を経ていないことは、国の裁量権の逸脱、乱用があったと認定した。
生活保護は、困窮の程度に応じ必要な金銭支給を行うことで、憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障し、自立を助けることを目的とした制度だ。司法判断は一般的に国の行政行為について広く裁量権を認め、その判断を尊重する傾向があるなかで、国民の生活を守る重要政策の手続きが十分ではなかったと最高裁が認定した意味は重い。
厚労省は、訴訟の原告に加えて当時の受給者全員に減額分を追加支給する検討に入っている。支給が行われれば、必要額は最大で数千億円規模に上り、事務手続きも膨大になるとみられる。
重要なのは、保護費を受給していた対象者が制度の趣旨である「最低限の生活」を営めているかどうかだ。現在の生活状況などを見極めるなどして、適切に対応してもらいたい。
自民党が12年の衆院選で公約に保護費の給付水準の低減を掲げており、厚労省の決定は、保護費を引き下げるとの結論ありきだったのではないかとの指摘がある。参院選では、政策のなかで生活保護制度の見直しなどに言及している党が複数ある。
新型コロナウイルス禍や物価高などにより、生活保護の申請は近年増加が続いている。制度の担うセーフティーネットとしての役割は極めて大きい。各党の主張を基に生活保護の仕組みの見直しを進めるにしても、十分なデータや専門家などの知見などを踏まえ、合理性と透明性を担保することが不可欠となる。厚労省はそれを肝に銘じるべきだ。