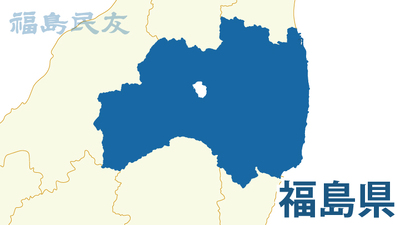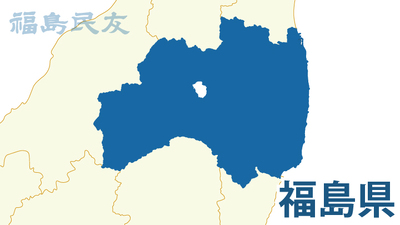- 生徒発の文房具支援が始動。現地とつないだライブ対話で“自分にもできる”が行動に -
10月22日、山形県遊佐中学校で、なかよし学園プロジェクトは「世界とつながる学び」講演会を実施しました。遊佐中学校では5月になかよし学園が行った人権教育講演をきっかけに、2年3組の生徒が自発的に文房具を収集し、海外送料を募金で集め始めています。
今回、学校を通じて依頼を受けたなかよし学園は生徒が集めた文房具を、学びの機会を欠く世界の子どもたちに届けることを正式に約束。講演では、ルワンダのパートナー団体「African mirror」の事例をもとに、文房具が「通学できる→就業につながる→収入が得られる→家族を支えられる」という正のループを生むことを紹介しました。

これまでに集めた文房具をなかよし学園に託す遊佐中学校2年3組
世界とつながる学び
“戦後0年”のシリアを知る:7~8月のシリア・プロジェクトでの支援と今後の計画を共有。焼け野原から立ち上がる人びとの姿に、生徒たちは強く心を動かされました。また、ニュースでしか聞いたことがないシリアで同じ日本から同世代の生徒児童たちが世界とつながる活動を行っていることを知り、生徒たちの中には「自分にもできるかもしれない」という気持ちが芽生え始めました。

なかよし学園が今年7月~8月にかけて行われたシリアプロジェクトの様子を紹介

シリアの戦争体験者の生の声から学ぶ生徒たち

シリアの戦争の経験を知り、当事者意識を持ち始める生徒たち
世界の“現場”と教室を直結:当日は、中村雄一代表がシリアのアラさん・アスレさんと教室をライブ接続。生徒は「そちらの学校は今どうなっていますか?」「一番うれしい日常は?」「日本から何が役に立ちますか?」と問いかけ、逆に現地からは「日本語の勉強が難しいこと」「いつか山形に行ってみたい」」など生の声を伝えていました。アラさんが「アリガトウ」を言い切った瞬間、教室は拍手と歓声に包まれ、言葉が贈り物になる感触が全員に伝わりました。

アレッポ大学で日本語を教えるアスレさんとテレビ電話をつなぐ

アレッポ大学で日本語を学ぶアラさんとテレビ電話をつなぐ

事務所が空爆によって破壊されたアラさん。シリアアレッポにて(中村雄一代表撮影)
メディアリテラシー・食の多様性(翌23日 特別授業):翌23日の特別授業では、3年社会科が「ジャスミン革命」を切り口に、“一つのニュースが世界を動かす”事例を紹介。SNS時代の今、誰もが情報発信者になるからこそ情報を批判的に見る大切さを伝えました。中村雄一代表は「真実って何だろう?」という問いからメディアリテラシーの話まで実践的な視点を共有しました。2年英語では異文化料理をテーマに、英会話の授業が行われ、中村雄一代表はカンボジアの昆虫食を例に食糧難とフードロスの論点に触れ、protein, sustainable, food loss などの語彙を押さえながら、賛否や代替案を英語で説明・意見表明することに挑戦。英語を“使うために学ぶ”手応えが生まれ、身近な行動(食べ残しを減らす、家庭の保存工夫を共有する等)へとつなげる視点が広がりました。
学校・地域の声
石黒 久 校長:「本校の理念は『人権感覚が豊かで成熟した子ども』を育むことです。今回の取り組みは、世界に視野を広げるだけでなく、身近な人を大切にする眼差しを同時に育ててくれました。講演とライブ接続で“遠い世界”が手の届く相手になり、子どもたちの表情が明らかに変わりました。出逢いは必然だと私は思います。この出逢いを今後も継続的な往還(CoRe Loop)の学びとして根づかせたいと考えています。」

ディスカッションタイムでは石黒校長先生も参加し、生徒たちと熱い議論を交わした。
教育クリエイター 今野 大輔 氏:「中村先生の現地の温度を帯びた話が入ると、難しいメディアリテラシーも“自分ならどう確かめるか”へ思考が一段深まります。現場の生の声を生徒たちが聞けたことで、受動的な“視聴”から能動的な学びへと切り替わりました。これから彼らの学びが世界で実装されるのがとても楽しみです。」

大阪万博で世界の様子を体感した今野教諭は「世界とつながる学び」を通してさらに世界を体感できると喜びを露わにした。
教諭 佐藤 真里 氏:「英会話の授業ではロールプレイングで生徒の“生の声”や伝えたい思いを英語で表現させたいのですが、実際には文法の定型文に頼り切ってしまう難しさがあります。そんな中、中村先生の授業ではカンボジアの食事風景を実例にしながら、場面と感情が結びついた“生きた英語”を学べ、とても参考になりました。もっと世界の話を生徒に聞かせ、表現が“型”から自分の言葉へ移る体験を増やしたいです。」

教科書に出てくる世界を「リアル」に見せたなかよし学園の授業に先生・生徒は興味津々だった。
教諭 田中 綾 氏(2年3組担任):「なかよし学園の講演を聴き、道徳のSDGs単元から始まった“文房具を集めよう”という試みは、想像以上に役割の多様化を生みました。普段は前に出ない子が募金箱や段ボールのデコレーション、ポスター作成、仕分け表の作成で中心になったり、保護者への周知、校内掲示まで、見える運営にしたことで、クラス全体の結束が高まりました。生徒たちの想いが文房具に込められ、必要とする人たちに届くのがとても楽しみです。」

今後は保護者会等で寄付を募り、なかよし学園からも現地での写真や動画を提供する。
生徒発の広がり
2年3組の「一歩踏み出す勇気」は、校長・教職員、なかよし学園を巻き込み、他の学年クラスへと発展する学校横断のプロジェクトへと発展しつつあります。教室発の文房具支援に加え、講演後は他学年からも具体的なアクション案が続々と集まりました。たとえば、図書の読み広げと連動したオリジナル栞づくり(読書推進×国際交流)や、総合・家庭科と連携した地元野菜を使った食育支援(SDGs〈2・12〉に接続)など、教科横断で実装可能な小さな一歩が束になって動き出しています。
校内では「集める→仕分け→届ける→反応が“里帰り”→振り返り」のなかよし学園CoRe Loopモデル運用を前提に、回収方法や掲示・周知、振り返りジャーナルの書式まで実務の型を整備中。主役は子どもたちで、有志を核に学年や委員会を横断する実行チームが生まれ、“受け手から担い手へ”の主語転換が可視化されています。単発の善意で終わらせず、成果と手応えが循環する仕組みを校内に据えた点が、ニュースとしての価値-再現性と拡張性-を持つ取り組みです。

これまでも多くの国で日本の生徒児童のグローバル化を育んできたなかよし学園(ルワンダ)

これまでも多くの国で日本の生徒児童のグローバル化を育んできたなかよし学園(南スーダン)

これまでも多くの国で日本の生徒児童のグローバル化を育んできたなかよし学園(ケニア)
今後の展開
集まった文房具はなかよし学園がシリア・ルワンダ・カンボジア・南スーダンなどに届け、現地からの手紙・写真・短い動画などの反応を学校へ“還流”します。さらに、児童生徒のアイデアを教材化→海外授業で実装→現地校と共創→反応の里帰りへと循環させるCoRe Loop(Co-create & Return Loop)で、“支援される側から支援する側へ”の主語転換を促します。
※本プロジェクトは経済産業省採択・全国50校で展開中。
団体概要
団体名:特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト
代表者:中村 雄一
所在地:〒270-0021 千葉県松戸市小金原4-14-14
事業:教育支援/平和・防災教育/探究学習設計/海外(アフリカ・中東・アジア)での教育協働
公式サイト:http://www.nakayoshigakuen.net/npo/index.html
お問い合わせ(報道・学校関係者)
特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト(事務局・広報)
担当:中村 里英
TEL:047-704-9844
E-mail:nakayoshigakuen.office@gmail.com
※写真素材・スライド引用可(要クレジット)。学校・自治体・PTA向け説明(対面/オンライン)に対応します。
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ