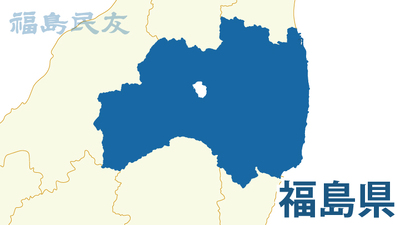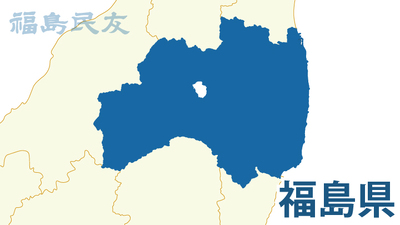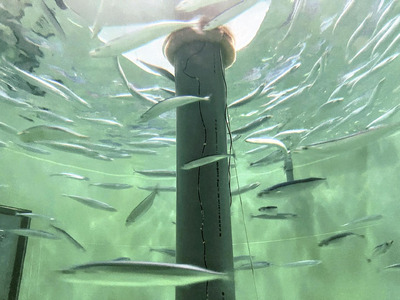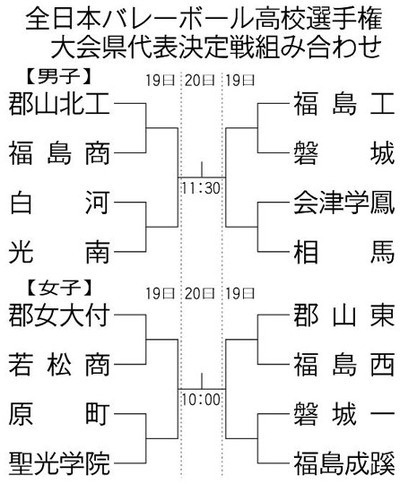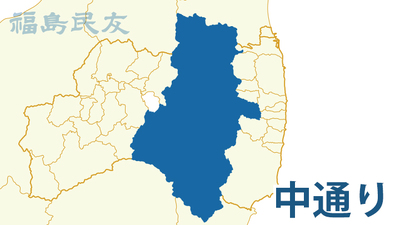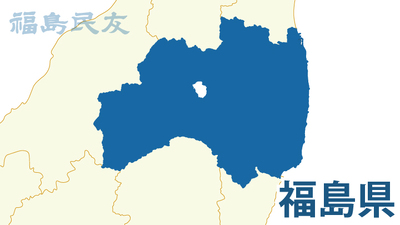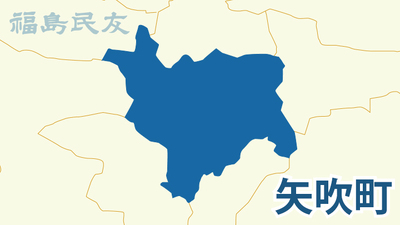「おくのほそ道」(以下「ほそ道」)の旅も、越後路を抜け、秋の訪れとともに終幕の気配が漂い始める。越中(富山県)、加賀(石川県)を行く、およそ足かけ26日間の紀行文を彩るのは「別れ」である。 1689(元禄2)年7月13日(陽暦8月27日)、市振(いちぶり)(新潟県糸魚川市)をたった松尾芭蕉と河合曽良は、目と鼻の先の境川を越え越中に入った。ここで芭蕉は、久々に歌枕の句を詠む。〈わせの香(か)や分...
この記事は会員専用記事です
残り1,642文字(全文1,842文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。