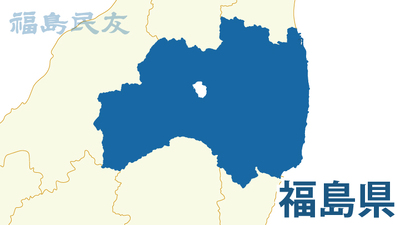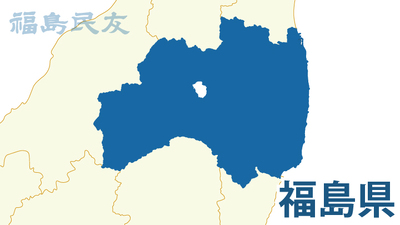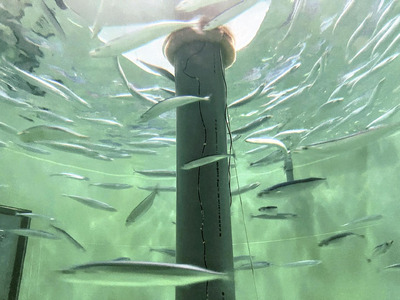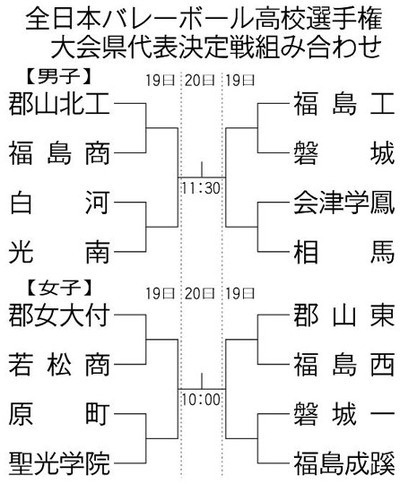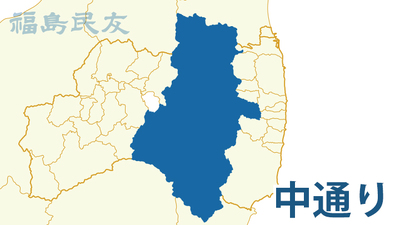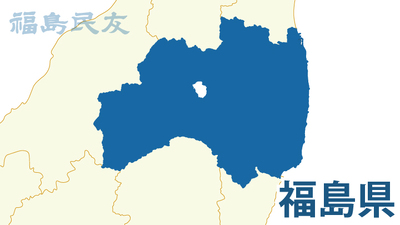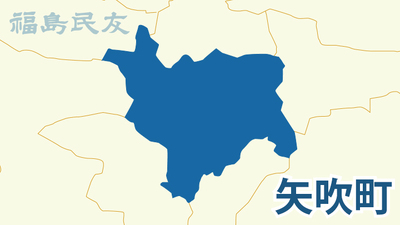「おくのほそ道」(以下「ほそ道」)の旅も、ゴールが間近に迫ってきた。越前(福井県)の旅である。変化に富んだ展開は、読み応え十分である。 と、その前に前回の続き。出発から松尾芭蕉と苦楽をともにした河合曽良が、病で別行動をとることになった。越前もそう遠くない山中温泉(石川県加賀市)の場面だ。実は金沢の門人立花北枝(ほくし)も同行していたが、曽良との別れはこの旅最大の事件である。 喜劇的な新相棒 ...
この記事は会員専用記事です
残り2,083文字(全文2,283文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。