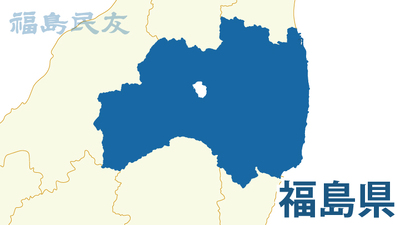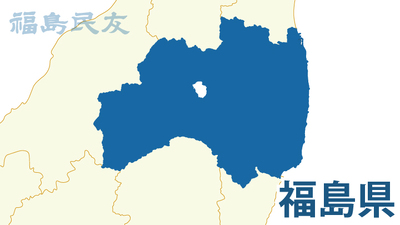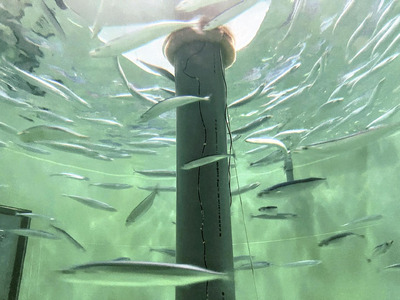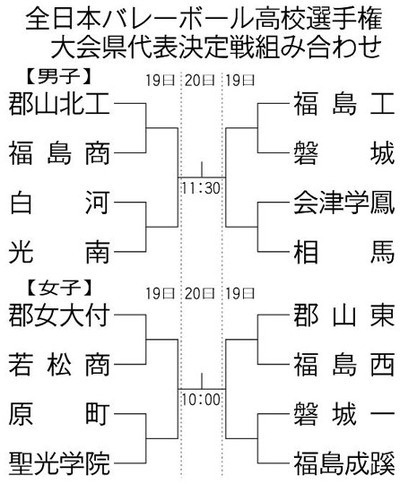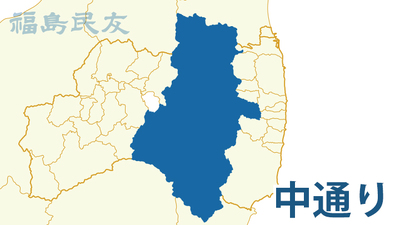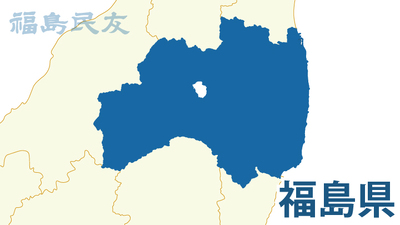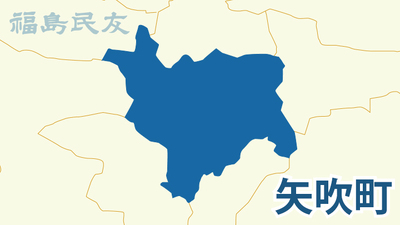「おくのほそ道」の旅を経て、松尾芭蕉の創作表現には変化が表れた。この旅の成果の一つが「かるみ」。さらに「不易流行(ふえきりゅうこう)」―変わらぬものと、変わりいくものの根源は同じ―という芭蕉のもう一つの俳諧理念も、この旅で見いだされたといわれる。では芭蕉は、どこで、どのように、この考えにたどり着いたのか。前回に続き、俳人の長谷川櫂さんに聞いた。 「おくのほそ道」の旅の成果として「かるみ」があると...
この記事は会員専用記事です
残り2,566文字(全文2,766文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。