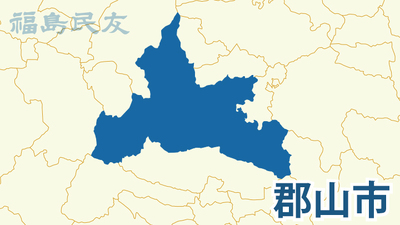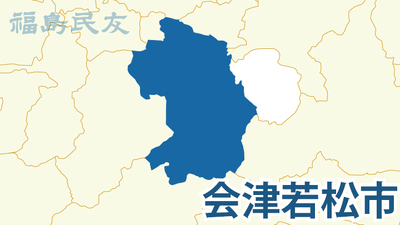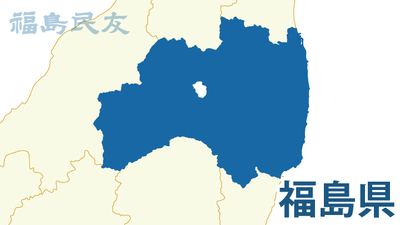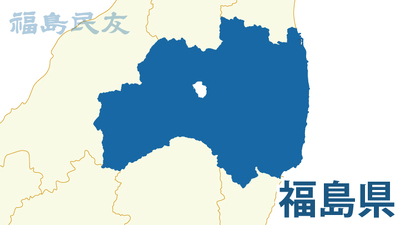脱炭素社会の構築に向けて太陽光発電施設の普及が急務とはいえ、災害対策などを軽んじる不適切な林地開発は許されない。行政が危険な開発行為を見抜き、ブレーキをかけることが重要だ。
県内の山林に太陽光発電施設を設置する事業者が増える中、先行して整備すべき災害対策用の調整池などが後回しにされたり、土砂が流出したりするトラブルが相次いでいる。県が昨年、開発を許可した工事中の計202件を調査したところ、太陽光発電施設を中心に12件で違反行為があった。
県は新年度から、違反行為や土砂流出など被害の発生で、工事中止の指示や命令を受けた事業者名などを公表する。災害を誘発しかねない開発の抑止につなげる。
トラブルが後を絶たない現状を踏まえれば、違反事業者名の公表は妥当だ。県は、公表に加え、指導を重ねても事業者の対応が改善されなければ許可を取り消すなど、厳しく対処する必要がある。
県によると、違反事業者を公表している都道府県は五つほどだ。地元以外の事業者が開発しているケースがあるため、個別の自治体の対応では制裁の効果が薄い。
国は、対応を自治体任せにせず、違反事業者の情報を全国で共有する仕組みをつくるべきだ。悪質な事業者は一定期間、林地開発ができない罰則を設けるなど、踏み込んだ対策が求められる。
県は、小規模な林地開発の規制も強化する。近接する複数の計画の一体性の有無を判断する現行基準は、開発時期が重なるか、続く場合となっている。新たに「前の開発完了から5年以内に次の開発を行う場合」を加える。
福島市では、大規模太陽光発電施設の近くに、小規模な発電施設が立て続けに整備された事例がある。一体的な開発であれば災害対策が義務付けられていたが、県は、開発期間が空いているなどとして一体性がないと判断した。
開発期間が空いているか否かにかかわらず、面積の拡大に応じて災害対策を強化するのが筋だ。県は、小規模開発の届け出を受ける市町村と連携し、対策が抜け落ちる穴をふさがなければならない。
県は現在、防災措置が完了した段階での現場確認や、住民からの苦情などを基にした調査を行っている。ただ、林地での太陽光発電施設の急速な拡大に対して監視が行き届いていないのが実情だ。
新たに県は、開発を許可した全ての事業を対象に現地を調査するとしているものの、人員の確保が課題だ。県は、早急に監視体制を強化することが重要となる。