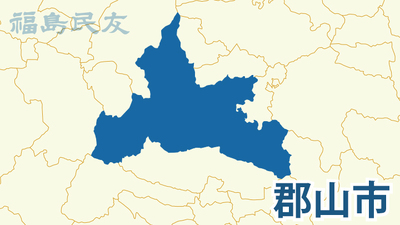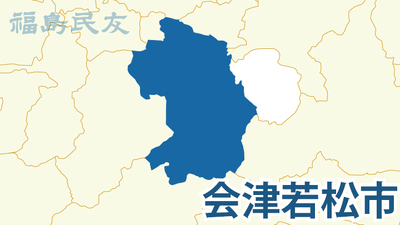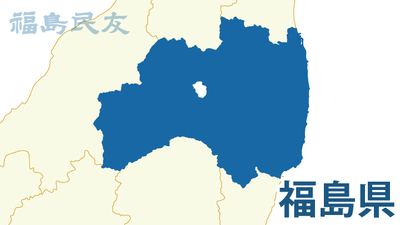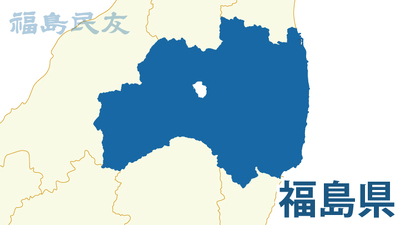福島市と宮城県柴田町を結ぶ第三セクター鉄道の阿武隈急行は、住民の生活や観光などに欠かせない広域インフラだ。鉄道の価値を高め、さらに地域から必要とされるよう、沿線自治体など関係機関が知恵を絞る必要がある。
利用者数の低迷や災害の影響などで赤字経営が続く阿武隈急行を巡り、宮城県側が1月、鉄路を維持する方針を示した。本県区間に比べて利用者数が少ない宮城県側は2年ほど前から、バスなどへの転換も含めて検討してきた。
バスへの転換はコストを抑えられる一方、鉄道に比べて移動時間が延び、利便性が低下する。加えて、人手不足でバスの運転手確保の難航が予想されることから、本県側は早々に鉄路維持の方針を固めていた。宮城県側も同様の理由で方針を決めたとみられる。
ピーク時の4割減とはいえ、2023年度は延べ約190万人が阿武隈急行を利用した。路線全体の需要や、バス転換のメリットとデメリットを踏まえ、鉄路の維持を決めた両県の判断は妥当だ。
鉄路維持の方針で一致したことにより、経営改善策の本格的な議論が始まる。阿武隈急行線沿線地域公共交通協議会長の吉田樹福島大教授は1月の会合で、今後の議論に向けて「鉄道の維持を決めたことがゴールではない。目的は地域を維持すること」と語った。
方針決定までの議論では、鉄路維持が前提の本県側に対し宮城県側の足並みがそろわず、県境を挟んで温度差が鮮明になった。背景には、赤字を穴埋めする財政負担の考え方などに自治体間で違いがあったと指摘されている。
人口減少で利用者数のさらなる低迷が見込まれる中、鉄路を維持する目的が曖昧ではバス転換などの議論が再燃しかねない。福島、宮城両県と沿線自治体には、明確な目的の共有を求めたい。
関係者の中には、株主の沿線自治体が事業計画の立案や鉄道事業の基盤強化などに、より積極的に関わることを求める声がある。車両運行などを担う鉄道会社のできることには限界があるからだ。
例えば、少子化に伴う学校再編の計画が浮上しても、駅前に新たな学校を建設することは鉄道会社にはできない。しかし、第三セクターの経営に携わる自治体であれば、学校と駅を連動させたまちづくりが不可能ではないだろう。
駅前に公共施設や医療機関を集約するなど、人口減少に適応したまちづくりの視点が必要だ。地域が生き残れるかどうかは、沿線自治体が協働し、阿武隈急行をどう生かすかに懸かっている。