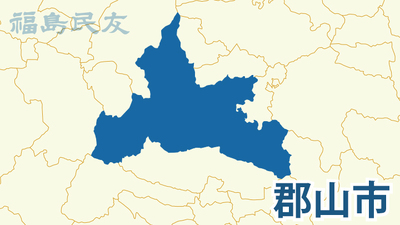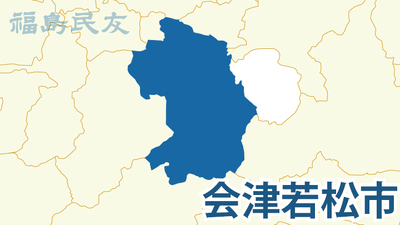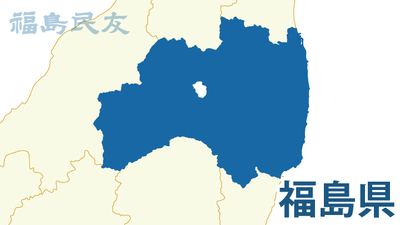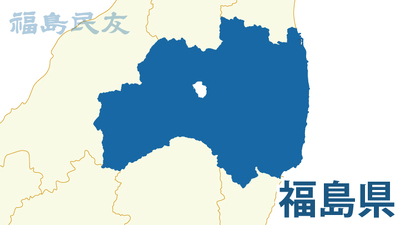高校の授業料を実質無償化する国の制度が拡充される可能性が高まっている。私立に通う生徒への就学支援金を現行より6万円ほど多い「45万7千円をベース」に引き上げることなどについて、自民、公明両党と日本維新の会の3党が詰めの協議を行っている。
現行の支援で公立は実質無償となっている。学業やスポーツなどで特色ある教育を提供する私立は公立より授業料が高く、施設使用料などの負担もある。引き上げ額は全国平均から算出された。
支援金が拡充されれば、経済的な理由で私立への進学を諦める生徒が減り、希望する教育を受ける機会の確保につながるとされる。国より手厚い支援を独自に実施している大阪府や東京都と、その他の道府県との地域格差を埋める必要性も指摘されており、拡充の意義は理解できる。
支援金拡充の協議が急速に進んだ背景には、政府の2025年度当初予算案を3月中に成立できなければ、国民生活に混乱を来しかねないという少数与党の危機感がある。無償化の実現を掲げる維新の要求を受け入れる代わりに、予算案への賛同を得たい考えだ。
看過できないのは、支援の上積み額などの折衝に終始し、拡充が与える影響への議論を深める姿勢が与野党ともに希薄なことだ。国の根幹を成す教育政策を政治的な打算で進めるべきではない。
私立が多い大阪や東京では、教育内容が多様で施設などが充実した私立に人気が集中し、定員割れする公立が増えた。全国一律で支援金が拡充された場合、地方で何が起きるのか。国は影響を見極めるため、進学ニーズなどに基づく検証を進めることが急務だ。
県内の全日制の高校は公立77、私立17となっている。県内の私立を志願する生徒が増えても、定員が大幅に増えない限り、大都市のような公立の定員割れが直ちに起きるとは考えにくい。
所得が比較的多い世帯の場合、支援金の拡充で余裕が生まれた分を学習塾の費用などに回せる。大学進学やスポーツなどで実績のある県外の私立に通う経済的なハードルは、収入が少なく遠方への通学費や下宿費などを捻出するのが難しい世帯と比べて低くなる。
支援金の拡充は、所得の多い世帯や私立が多い都市部の生徒への優遇効果がより高いといえる。高校は大学への進学や就職など将来の進路を決める重要な場だ。世帯収入や住んでいる場所によって新たな格差が生じぬよう、国は、経済的負担の少ない公立の教育環境の充実などにも注力すべきだ。