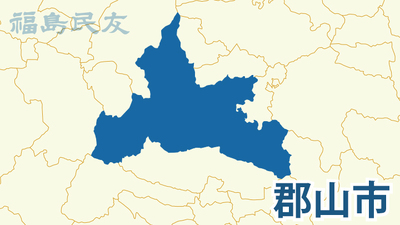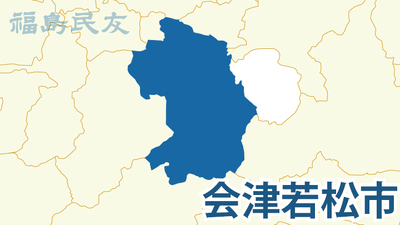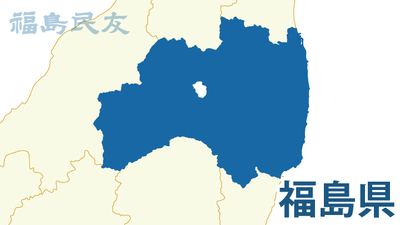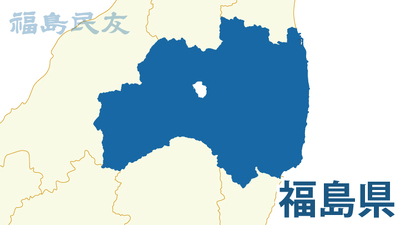障害者と共に生きる社会を実現できるかどうかは、健常者の意識の変革と行動に懸かっている。司法からのメッセージを一人一人が受け止めることが重要だ。
聴覚障害のある11歳の井出安優香(あゆか)さんが重機にはねられて亡くなり、将来働いて得られるはずだった逸失利益が争われた損害賠償請求訴訟の控訴審で、大阪高裁は、障害を理由に減額せず健常者と同等とする初めての判断を示した。判決は今月5日に確定した。
就労前の子どもの逸失利益の算定には全労働者の平均年収が用いられる。ただ障害児は、障害が労働能力を制限するという理由で健常者の70~80%程度に減額されてきた。今回の一審判決でも、なぜ障害が能力を制限するのか十分な説明がなく85%と判断された。
これに対し高裁判決はまず、井出さんに学年相応の知識などがあり、コミュニケーション能力が高かったと認定した。その上で、補聴器の高性能化が著しく進んでいることなどを踏まえ、健常者と同等に働くことが可能であり、減額する理由はないとした。
健常者より障害者の労働能力が劣るとする考え方は、司法を含め社会に深く根付いているとみるべきだろう。高裁判決は社会通念を退ける画期的な判断だ。
高裁判決のポイントの一つは、子どもの逸失利益を認定する新たな判断の枠組みを示したことにある。一般的には個別の能力を問わず全労働者の平均年収を用いるのが通例であり、減額が許容されるのは、全額を認めるのに「顕著な妨げとなる事由がある場合に限られるべきだ」とした。
障害の有無にかかわらず減額は例外とする考え方だ。障害の程度などによっては減額される可能性が否定できないものの、同種の訴訟で、新たな枠組みに基づく判例が定着することを期待したい。
改正障害者差別解消法が昨年4月に施行され、行政のみならず民間事業者にも、障害者の社会参加を妨げる障壁を取り除く合理的配慮が義務付けられた。聴覚障害者の求めに応じ、手話や文字通訳、音声認識アプリを活用するなどして働きやすい環境を整えることが合理的配慮に当たる。
障害者法制の進展を踏まえた高裁判決は、コミュニケーションの方法を音声に限る意識や習慣こそが、聴覚障害者にとっての社会的障壁になっていると指摘した。周囲の理解や配慮次第で障壁は取り除けると言い換えられよう。障害者が差別や偏見を受けずに、能力を発揮できる環境整備を社会全体で推進することが大切だ。